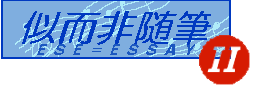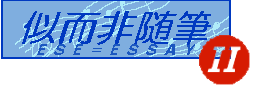|
これまで、「幻想曲」について考えたり、「キャラクターピース」について考えたり、はたまたロンド形式、フーガ、変奏曲などについていろいろ考えたりしてきました。
この流れで行くと、そろそろソナタ形式についても考えるべき時期かもしれませんが、この形式はなかなか一筋縄で行きそうになく、私もきちんと論文として書くべきなのではないかと思ったこともあるくらいで、くだけた形で日誌に書くにしても、もう少し材料を集めてからにしたいと考えます。
その前に、「ソナタ」についてちょっと考えてみようと思います。
言うまでもなく、「ソナタ」と「ソナタ形式」は混同されやすいものの、概念としては異なっています。「ソナタ」は「カンタータ」に対応する言葉で、鳴り響くという意味であり、基本的には器楽曲の一形態です。器楽の音楽が歌や舞踊の伴奏から離れて、それ自体を目的として作られるようになって以来作られ続け、バロック時代にはひとまずの形式的な完成を見たものの、その後古典派時代になって少し違った構造を持つ楽曲を指すようになりました。その後現代に至るまで「ソナタ」は作られ続けていますが、古典派時代にこの「ソナタ」の冒頭楽章に用いられるものとして整備された形式のことを「ソナタ形式」と呼ぶのです。
古典派前期くらいまで、トリオ・ソナタというような、数人の奏者によるアンサンブルを必要とするソナタも書かれていましたが、その後は主に独奏曲について言われる言葉になりました。アンサンブルによるものは室内楽曲と呼ばれ、三重奏曲、四重奏曲などの言葉を与えられましたし、オーケストラによるものは交響曲、独奏楽器(ときには複数)とオーケストラによるものは協奏曲などと、術語が分化しました。ただ、少なくとも古典派からロマン派頃までのものはいずれも似かよった構造を持っているため、石桁真礼生先生は総称する呼び方として「ソナタ構造」という言葉を提唱しておられました。ただしあまり一般的にはなっていないようです。
今回考えてみたいのは、この「ソナタ」のほうで、「ソナタ形式」はまた後日にまわしたいと思います。 ごく初期には、たとえばゆっくりした舞曲と速い舞曲を組み合わせて(「メヌエットとガリアルド」みたいな形)、その2曲で「ソナタ」と呼んだりしていたようです。
しかし、いちおうバロック・ソナタとして整備された形としては、緩・急・緩・急という速度配列の4楽章から成る組曲でした。
そこに至るまでにも、「教会ソナタ」と「世俗ソナタ」の両派があって、世俗ソナタのほうは舞曲を中心とした曲種から構成されていたようです。これはバロック末期には組曲、あるいはパルティータという名前で定着しました。
J.S.バッハに『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』という曲集があります。この曲集は過去、誤って『無伴奏ヴァイオリンのための6つのソナタ』と呼ばれていたこともありました。ただしその名称がまるっきりの嘘っぱちであったかというとそうでもなくて、パルティータのほうはその昔の世俗ソナタだったのですから、「3つの教会ソナタと3つの世俗ソナタ」というタイトルでも良かったわけです。ちなみに有名なシャコンヌはパルティータ第2番の終曲です。
ついでですので、この曲集によってバロック・ソナタの一般的な構造を見てみましょう。3曲のソナタは、いずれも大同小異の形式をもって作られています。緩・急・緩・急という速度構成を持つことは上述しましたが、第一楽章はアダージオとかグラーヴェといった速度標語を持ち、序曲風の堂々とした曲想を伴っています。細かい音符を多用しているのも共通しています。
第二楽章はいずれもフーガになっています。無伴奏ヴァイオリン1挺だけで多声音楽であるフーガを作ってのけるのだからバッハのフーガ好きには驚くべきものがあります。ただし、バロック・ソナタの第二楽章が一般的にフーガであるということではなく、カプリチオのような曲想である場合もよくあります。
第三楽章はのびやかなアリア風の曲想になっています。第1番では舞曲のシチリアーナが採用されています。そして、このヴァイオリンソナタに関して言えば、この楽章だけ調性が異なっています。
終楽章は常動曲(常に忙しく動き回っている曲)のスタイルがメインです。このヴァイオリンソナタの場合、他の楽章には多用している重音をほとんど使っていないのが特徴です。
当然ながら、この時点ではまだ「ソナタ形式による楽章」は使われていません。ソナタ形式は、彼の息子たちが形を調えて、ハイドン・モーツァルト・ベートーヴェンの三傑に受け継がれつつ完成されることになります。
上にちょっと出たトリオ・ソナタというのも、バロック期に好まれた形態です。2本の旋律楽器と1本の低音楽器、それに和音を補強するためにハープシコードが使われました。だからトリオ(三重奏)という名前ですが、実際には4人での演奏となります。ちなみにハープシコード奏者には自分の楽譜は無く、低音を見て和音を構成しつつ即興で弾くのがお約束です。こういう低音のことを通奏低音(バッソ・コンティヌオ)と言います。
旋律楽器はヴァイオリン2本とか、ヴァイオリンとフルートとか、フルートとオーボエとか、いろんな組み合わせで可能です。低音楽器は古くはヴィオラ・ダ・ガンバ、その後はチェロやコントラバスなどが使われました。
形態はそのようでしたが、音楽としての構造は普通のソナタと同様です。バッハだと、『音楽の捧げもの』の中にあるトリオソナタが有名です。 これとまったく異なるソナタもありました。J.S.バッハと同い年のイタリア人、ドメニコ・スカルラッティが大量に作曲したタイプのソナタです。これは全然組曲の形になっておらず、単楽章で書かれています。仕えていた王女様のハープシコード練習用に書いたのだと言われていますが、だとすると一種の練習曲の呼称としてソナタの名を使ったことになります。
もっとも、最近の研究だと、完全に単楽章というわけではなく、2、3曲を組にして演奏すべきだという説も出てきています。組となるべきソナタは、同じ調性で、速度が対照的になっているものが比定されています。
古典派前期のチマローザなどもこのタイプのソナタを書いています。
もしかすると、バッハのタイプの「ドイツ式ソナタ」と、スカルラッティのタイプの「イタリア式ソナタ」を分けて考えたほうが良いのかもしれません。 さて、バッハの息子たちも「ソナタ」という名の曲をたくさん書いていますが、親父の書いていたバロック・ソナタとは全然違う形で、この時期の「ソナタ」になぜこんな大変化が起こったのか不思議です。
バッハの息子たちが書いたソナタ(前古典派ソナタ)の典型的な構造は、急・緩・急の三楽章制で、第一楽章はソナタ形式的であり、第二楽章は簡単な伴奏の上にのびやかな旋律が流れるいわゆるギャラント・スタイル、第三楽章は活溌もしくは激しさを持った「おひらきのフィナーレ」といったタイプの曲でした。上に書いたバロック・ソナタと較べると、最初の楽章が欠落したとも言えますが、これはむしろ協奏曲のスタイルを採り入れたというのが真相に近いのかもしれません。
協奏曲は、それまでソナタとは別個に発達してきていたジャンルで、親父バッハにもブランデンブルク協奏曲というのがありますし、もっと知られているのはヴィヴァルディの『四季』などです。こちらは基本的に三楽章制で、やはり急・緩・急という速度構成を持ち、その曲想も上に書いた前古典派ソナタと共通しています。
息子バッハたち(それなりに有名な人だけでも4人は居ます)は、ソナタという独奏曲形態に協奏曲の内容を採り入れて、新しいスタイルのソナタを作り上げたようです。なお、親父バッハにも「イタリア協奏曲」という、ハープシコードでひとりだけで弾く協奏曲があり、それもヒントになったかもしれません。
このため、初期のソナタは三楽章制というのが普通でした。ピアノソナタに限って言うと、ハイドンにもモーツァルトにも四楽章というのはありません(ハイドンのごく初期に1曲だけありますが、ほとんど習作と呼ぶべきもので、その後の四楽章制にはつながっていないようです)。クレメンティには後期にわずかながらあります。ところがベートーヴェンは第1番から四楽章制でした。これも謎のひとつです。
ちなみに、ケルビーニのソナタを見ると、ほとんど二楽章制です。どういう理由なのかわかりませんが、イタリア式単楽章ソナタが、ドイツ式多楽章ソナタに妥協してゆく過程ということなのかもしれません。なおクレメンティはイタリア人ではありますが、早い時期から国外で勉強をしていましたので、イタリア式の構成法などには染まっていなかったのだと思われます。
ソナタは三楽章制が主流でしたが、似た構造を持つ弦楽四重奏曲などの室内楽曲、あるいは交響曲は、なぜか終楽章の前にメヌエットを導入した四楽章制を採るのが普通でした。これも初期の頃は三楽章のものもあり、定型が出来上がるまでには時が必要でしたが、ハイドンやモーツァルトの中期以降はほぼ形が決まりました。室内楽曲や交響曲にメヌエットが導入された理由も音楽史上の謎と言って良いのですが、かつての世俗ソナタの要素が忍び込んできたのかもしれません。なお、協奏曲は「三楽章」というイメージが強すぎたのか、今に至るまで三楽章制がほとんどです。ブラームスのピアノ協奏曲第1番が四楽章を持っていますが、あれはもともと交響曲として計画された例外的な存在と見るべきでしょう。
ベートーヴェンは、ピアノソナタを室内楽曲や交響曲と同等なものと考えたのかもしれません。それで最初から四楽章を採用したのだと思います。ただ、第2番で早くも、メヌエットのかわりにスケルツォを入れました。舞曲という縛りが邪魔に感じられたのでしょう。
ところで、ハイドンのソナタを眺めてみると、単純に急・緩・急の三楽章というものばかりではないことに気がつきます。有名なので「ソナタアルバム第1巻」に掲載されているソナタを見てみますが、最初のハ長調(第48番)はソナタ形式の第一楽章、ゆっくりした第二楽章に続いて、終楽章がメヌエット(と明記されてはいませんが、スタイルからしてメヌエットです)となっています。次のト長調(第42番)は第二楽章に緩徐楽章の代わりにメヌエットを用いています。ニ長調(第50番)は正常な形ではありますが、第二楽章がきわめてシンプルで、ほとんど終楽章の序奏のような規模でしかありません。嬰ハ短調(第49番)は第二楽章に「スケルツァンド」と題された速い楽章が入り、第三楽章にメヌエットが置かれています。ホ短調(第53番)に至ってようやく「普通の構成」になっています。
モーツァルトのピアノソナタが、「トルコ行進曲付き」を除いてほぼどれも定型どおりであることを考えると、このハイドンの「いろいろやってみた感」は特筆に価します。他のソナタを見ても感じるのですが、ハイドンはのちにベートーヴェンが確立した ソナタ形式の楽章
ゆっくりした楽章
メヌエットまたはスケルツォ
華麗な終楽章 という四楽章制ソナタ定型の、「どれかひとつを省略してみた」というやりかたで三楽章を構成しているように思えてならないのでした。彼の頭には、やはり室内楽曲や交響曲があったのかもしれません。そして弟子のベートーヴェンは、
「それなら省略せずに全部使っちゃえばいいじゃん」
とばかりに四楽章制ソナタを創始したというところだったのかもしれませんね。 ベートーヴェンは四楽章制ソナタを創始したとはいうものの、32曲のピアノソナタのうち四楽章を備えているのは10曲、終楽章前にかなり長大な(独立した楽章と呼んでも良いような)序奏がついている準四楽章制のものを含めても13曲でしかありませんでした。
しかし、その後の作曲家たちは四楽章制を「基本」と考えたようです。
シューベルトのピアノソナタは、初期のものは未完成品が多く、終楽章が欠落していたりします。また五楽章(スケルツォが2つ入る)というのがひとつありますが、これは本当にソナタとして構想されたのかどうか微妙です。中期以降は三楽章のものと四楽章のものが混在していますが、どちらかというと四楽章制を主流と見ていたように思われます。
ヴェーバーになると4曲のピアノソナタが残っていますが、第3番が三楽章であるほかは四楽章となっています。
ショパンとシューマンはそれぞれ3曲ずつピアノソナタを書いています。すべて四楽章を持っています。
リストは1曲だけピアノソナタを書きましたが、これはベートーヴェン以降もっとも構造的に意欲を見せたものであるかもしれません。単楽章のソナタというものを復活させたのです。
とはいえ、それはかつてのイタリア式単楽章ソナタではなく、「ソナタ形式」と「ソナタ」の結合というアイディアでした。つまり、 ソナタ形式の呈示部=ソナタの第一楽章
ソナタ形式の展開部=ソナタの第二楽章
ソナタ形式の再現部=ソナタの終楽章 という構造の類似性に眼をつけ、両方を一緒にしてみたというわけです。かくて小節数は800小節近く、演奏時間は30分近いという厖大な単一楽章の曲が誕生しました。終楽章に相当する再現部では、主題がフーガの形(ベートーヴェン以来、ソナタの終楽章によく使われるようになった)で出てくるなど、いろいろ工夫しているのが観てとれます。
これに先立って、メンデルスゾーンがソナタや協奏曲などを切れ目無しに演奏するという形を創始していますが、これは各楽章の間にブリッジを設定して、緊張感を失わないままに次につなげるというだけの意図で、構造的に新奇なものを考えたわけではありませんでした。
後期ロマン派になると、ソナタはあまり作曲家にとって重要なジャンルではなくなってきたようで、構造にもさほど工夫を凝らしたという形跡がありません。1、2曲は作るけれどもそれだけという人が多いようです。
その中で、フランクのヴァイオリンソナタは少し特異な位置を占めていると言って良いでしょう。
まず、バロック・ソナタ以来の、緩・急・緩・急という速度構成が、意図してか偶然にか復活しました。まあ、ベートーヴェンのピアノソナタ第12番もそうなっているのですが、フランクのソナタの場合は、第一楽章を前奏曲的に扱い、はっきりと第二楽章に重みを置く構造を採っています。これは彼の愛用したモティーフ循環スタイルの要請によるもので、第一楽章ではまだ循環素材が充分に揃っていないために軽めの曲にしてあるわけです。 近代以降でソナタをたくさん作ったのはロシアの作曲家が多い気がします。中でもスクリャビンは10曲、プロコフィエフは9曲のピアノソナタを書いており、自分の作曲活動の中でも主要なものと位置づけている気配があります。
スクリャビンのソナタは、第1番と第3番が四楽章、第2番と第4番が二楽章を持ち、第5番以降はすべて単楽章となっています。ただし、リストのような、他の構造原理を折衷したということはなく、普通にソナタ形式の楽章がひとつあるだけです。
四楽章を持つ2曲も、その配置は素直でなく、第1番は急・緩・急・緩という珍しい構成になっています。第3番はフランクのソナタと同様緩・急・緩・急ですが、第一楽章がそれなりにドラマティックで重みがあり、第二楽章は軽いスケルツォになっているところが違っています。
プロコフィエフのピアノソナタは、第1番と第3番が単楽章、第2・6・9番が四楽章制、残りが三楽章制です。速度構成などはいずれも標準的と言って良さそうです。
なおヒンデミットは「オーケストラのすべての楽器のためにソナタを書く」という遠大な計画を立て、かなりの程度達成しましたが、どちらかというとバロック的な軽いものが多く、ベートーヴェン以来多くの作曲家がまなじりを決して取り組んできたソナタとは少し毛色が異なります。
近代以降に書かれたソナタは、単楽章であるか、多楽章にしても三楽章しか持たないものが多くなったように思われます。ソナタという名称の作品ばかりでなく、古典派以来四楽章制の牙城であった交響曲や室内楽曲でも、三楽章のものが大半になってきました。「スケルツォ」という存在、軽やかでほっとひと息つけるような曲想の楽章が、深刻ぶりを是とする20世紀には扱いづらくなってきたのかもしれません。
「ソナタ」はまだこれからも書かれることでしょうが、21世紀のソナタとはどういうものであるべきなのか、作曲家は考えてゆく必要がありそうです。
(2017.2.4.)
|