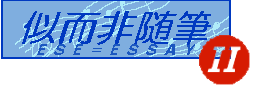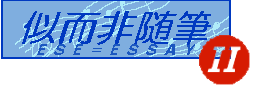|
音楽の分野で「キャラクターピース」という言葉があります。訳して「性格的小品」と呼ばれることも多いようです。
ソナタ、フーガなどは、ある決まった形の構造につけられた名称ですので、これは作曲者が違っても、時代が違っても、同じ名称で呼ばれています。一方、「花の歌」とか「森の水車」のように、その曲だけにつけられたタイトル(=標題)を持つ曲もあります。キャラクターピースというのはその中間と言えば良いでしょうか、曲の構造が決まっているわけではありませんが、名前どおり「性格」が似かよったグループを指しています。だから同じタイトルで別の作曲者が書くこともあり得るわけです。
その性質からして、ロマン派の時代にたくさん作り出されたことは想像がつきますが、いくつかの種類についてはずいぶん古いものもあります。
他項で触れた「ファンタジア(幻想曲)」などもそのひとつと考えて良さそうです。これはバロック初期から名前が見受けられますので、キャラクターピースと考えた場合にはいちばん古いものに属するかもしれません。
「プレリュード(前奏曲)」「ウヴェルチュール(序曲)」のように、もともとは読んで字の如く組曲やオペラなどの冒頭に置かれていた曲種も、のちに独立して作られるようになってキャラクターピース化したケースがあります。ショパン、ラフマニノフ、スクリャビン、ショスタコーヴィッチなどが、それぞれに「24の前奏曲」というような曲集を書いていますが、これらは何かの前に置かれているわけではなくてまったく独立したものです。一方、序曲のほうは主にオーケストラ用のキャラクターピースとして発展しました。ベートーヴェンの3曲の「レオノーレ序曲」は、いずれもオペラ「フィデリオ」に関連して書かれはしましたが、内容的にそれほど密接ではなく独立した楽曲と考えて良いでしょう。メンデルスゾーンの「フィンガルの洞窟」になると、そういう名前のオペラや組曲は全然無くて、最初から演奏会用に独立して書かれた序曲となっています。この段階になると、ほとんど「交響詩」とあんまり変わらない内容を持つようになっています。
「インテルメッツォ(間奏曲)」というのも、もとはオペラやバレエの幕間とか、組曲の中に置かれた曲種で、いわば全体の中での位置を示すだけの言葉だったのが、ブラームスあたりから独立楽曲化しました。前奏曲よりもさらに淡いイメージの小品であることが多いようです。近代ではプーランクなどが好んで書きました。
以上はもともとの立ち位置が決まっていた曲種が、だんだん独立したというものですが、その他にはどんなものがあったでしょうか。
バッハの組曲類を見ると、18世紀前半頃にどのような曲種があったのかよくわかります。彼の『フランス組曲』『イギリス組曲』『パルティータ』の3つの組曲群は、基本的には4つの舞曲──ドイツ舞曲アルマンド、フランス舞曲クーラント、スペイン舞曲サラバンド、英国舞曲ジーグ──を軸とし、その前に前奏曲をつけたり、サラバンドとジーグの間に別の種類の曲を入れたりして構成されています。この「別の種類の曲」は、メヌエット、ガヴォット、ブーレといった舞曲であることが多いのですが、時には舞曲でないものも含まれています。エア(アリア)、カプリチオ(狂想曲)、スケルツォ、ブルレスカといったところで、これらはロマン派以降でもたくさん書かれた曲種です。
このうち、エアというのは要するに「歌」のことです。「ロンドンデリー・エア」という時のエアですね。ただしバッハの組曲中のエアは、インヴェンション風の小品といった趣きがあります。
カプリチオとスケルツォは、のちにはわりと大規模な作品が書かれるようになり、その性格もだんだん変化しましたが、バッハの時代にはまだ「気まぐれ」「おふざけ」という原義が残っているように思われます。どちらも、古典派後期くらいから徐々にイメージが変わり始めました。
スケルツォに関しては、ベートーヴェンがそれまでのメヌエットに代えてソナタや交響曲の中で使いはじめたのが、その後の性格決定に大きな影響を及ぼしたような気がします。ベートーヴェンがなぜメヌエットの代わりにスケルツォを入れることを考えたのかわかりません。メヌエットという「舞曲」の性格に限定されないものが欲しかったのだろうとは思いますが、スケルツォを選んだ理由は謎です。ともあれソナタや交響曲に定席を占めるようになったスケルツォは、だんだん最初の「おふざけ」の意味が失われて、むしろ情熱とか熱狂といったキーワードがふさわしい曲種となりました。ショパンの4曲の独立したスケルツォが決定的だったと言えるでしょう。
それに較べると、カプリチオのほうは、もともとの意味である「気まぐれ」という性格を保持したようでもあります。ただし、形式的に奔放というわけではなく、曲想の上での気まぐれさを示していることが多いようで、形式としてはロンド形式とか変奏曲とかが用いられるケースがよく見受けられます。
ブルレスカというのはあまり聞き慣れないかもしれませんが、英語で言えばバーレスクで、漫談とか寸劇を意味します。これも愉快な、おふざけの強い曲想で、スケルツォのように多用されなかったせいか、その性格は後世にも伝わったかもしれません。メシアンの若い頃のピアノ曲「幻想ブルレスク」などはまさに「漫談・寸劇」のイメージを残している感じです。
ベートーヴェンは「バガテル」という小品をかなりたくさん作曲しています。中期に7曲、晩年に11曲と6曲からなるまとまったバガテルを作っていますが、有名な「エリーゼのために」も一種のバガテルであると考えられ、他にもバガテルという名は称していないけれど明らかにバガテルだ、という作品がいくつか存在します。
「バガテル」というのは「つまらないこと、無駄話」といったような意味で、ソナタや交響曲のようなかっちりとした楽曲を書く息抜きに、思いつくままに書き記したような印象を受けます。中期の7曲のバガテルは、そこそこの長さもあって形式もわりにはっきりしていますが、晩年の11曲の組などは、1行で終わってしまうような本当に断片的な楽想も含まれていて、ベートーヴェンの一面をかいま見ることができてなかなか興味深い作品となっています。
サンサーンスやシベリウスなどがこの名称で小品を作曲しています。私もヴォカリーズとピアノのためにバガテルを書いていますし、学生時代に書いた「私事」というオーケストラ曲は確か「管弦楽のためのバガテル」という副題をつけておいたと記憶しています。
ヴェーバーは、「ロンド・ブリランテ」とか「モメント・カプリチオーゾ」とかのキャラクターピースを書いていますが、単語でないためかあまり追随者は出ていません。シューベルトになると「アンプロンプチュ(即興曲)」と「モメント・ミュージカル(音楽の瞬間)」という曲種を創始したことが知られています。これらは同じタイトルで書く人がたくさん出たので、名称としてポピュラーになりました。
即興曲というのは、字義通りには演奏者がその場で手すさびに弾いた曲ということになりますが、実際にはシューベルトにしろショパンにしろ、非常に整然とした三部形式をとっているものが多く、ただテーマのありかたが走句的でいかにも思いつきっぽいという点が特徴的と言えるでしょうか。
「音楽の瞬間」は「楽興の時」と訳されることが多く、即興曲と意味合いはあまり変わらないのですが、シューベルトは即興曲よりもっと規模が小さい小品にこの名を冠したようです。ラフマニノフの同名の曲はかなり長いものになっています。
メンデルスゾーンが創始したキャラクターピースとなると、「無言歌」が挙げられます。この名称はメンデルスゾーンの専売特許のようでもありますが、後世、若干この名を持つ楽曲を作った人も居ます。メンデルスゾーンは48曲の無言歌を作りましたが、意外にも自分ではそれぞれの曲にほとんど標題をつけていません。3曲の「ヴェニスのゴンドラの歌」と「二重唱」、それに「民謡」だけが作曲者自身の命名だとわかっていますが、標題というほどではありません。有名な「狩の歌」「春の歌」「つむぎ歌」など、あとはすべてのちの人が勝手につけた題名です。そもそも、標題音楽というものがはやりはじめたのはメンデルスゾーンが亡くなってもう少し経ってからの話で、彼の生前にはまだ、器楽曲にいちいち標題をつける習慣は無かったようです。
キャラクターピースといえばショパンと言えるかもしれません。今まで名前の出たスケルツォ、即興曲の他、ノクターン、バラードなどの曲種でいずれも名曲を残しています。ノクターンは英国のフィールドが創始したキャラクターピースですが、ショパンが続かなければ忘れ去られていたかもしれません。原義は「夜」で、そのため夜想曲という訳題が与えられました。ショパンに続いてはフォーレがたくさん書きました。私も1曲書いています。
バラードは中世の吟遊詩人の歌った物語詩ですが、器楽曲の名称として使ったのはショパン以前には私は知りません。いずれもポーランドの愛国詩人ミツケヴィッチの詩に基づいて作曲されているあたり、それなりのこだわりを感じさせます。もしかしたらミツケヴィッチがそれらの詩のことをバラードと呼んでいたのかもしれません。ショパンの4曲のバラードは、なぜか全部6拍子で書かれており、そのため現代のポピュラー音楽としてのバラードも6拍子が基本になっているようです。私がカラオケでちょくちょく歌う忌野清志郎の「スロー・バラード」も6拍子です。
もともとが「物語」ですので、バラードという曲種はわりと大規模な楽曲になることが多いようで、リストのバラードなどもかなり大がかりですが、その点ブラームスは比較的小規模なものが主で、似たような性格で大規模なものにはラプソディと名付けています。ラプソディというのは、とりわけ民族史的な内容を持つバラードと言って良いでしょう。「狂詩曲」と訳すのはあまり適当でない気がします。しかしリストの「ラプソディ・ウンガリッシュ」を「ハンガリー史詩」と訳してもピンと来ませんね。やはりここは「ハンガリー狂詩曲」でないとぴったりこないようでもあります。
シューマンもキャラクターピースには縁の深い作曲家です。というか、彼の作品はソナタなどまで含めて全部キャラクターピースではないかと思われるようなところがあるのですが、今まで挙げられていないもので後世に受け継がれた曲種としては、フモレスケ(ユーモレスク)、アラベスク、ノヴェレッテなどがあります。
フモレスケはむしろドヴォルジャークの作品が有名でしょう。ユーモアにあふれた小品というような意味合いですが、シューマンのことですから単に「可笑しみ」という意味だけでなく、古代以来の「体液(フモール)」のイメージも重ねていたかもしれません。
アラベスクというのは元来は「アラビア風の」ということですが、アラベスクと名付けられた曲を聴いても、あんまりアラビアっぽい印象は受けないことが多いと思います。シューマンが用いたアラベスクという言葉は、美術のほうで「唐草模様」を意味するアラベスクに違いなく、唐草模様のようにもつれあった曲想をイメージしたものでしょう。ドビュッシーのアラベスクもおそらくその流れだと思います。一方、子供がよく弾いているブルクミュラーの練習曲の中のアラベスクは、唐草模様をイメージした曲とは感じられません。これはバレエのアラベスク・ステップを意味していると思われます。
ノヴェレッテはノヴェル(小説)に指小辞-etteがついた言葉ですので、短編小説という意味になります。その意味ではバラードの一種とも考えられますが、散文である「小説」の名称を用いたところがシューマンらしいと言えましょうか。私の『少女追想』の副題は「女声合唱とピアノのための四つのノヴェレッテ」となっていますが、もちろんこの「短編小説」の意味合いを込めています。
スクリャビンは「ポエム」と題する小品をたくさん書いています。「詩曲」と訳されることが多いようです。1ページで終わってしまう文字どおりの小品から、晩年の「炎に向かって」のような大作までポエムと称しているので、果たしてスクリャビンがこの言葉にどんな統一的イメージを抱いていたのかわかりづらいところもありますが、そもそもポエム(詩)には短いもの長いもの、いろいろありますので、あまり限定したイメージにはこだわっていなかったのでしょう。
サティの「ジムノペディ」「グノシェンヌ」などもキャラクターピースのように見えますが、これらはサティ自身の造語なので、他の人にはイメージがつかみづらく、追随した人が居るという話は聞いたことがありません。ジムノペディは古代の青銅器に描かれたオリンピアの人物画のこと(つまり体操=ジムナスティクスに関連した言葉)だと説明されることがありますが、あんまりあてにはなりません。グノシェンヌもグノーシス(知識・認識)から来た言葉のようですけれども、それが曲想とどう関わり合っているのかはよくわかりません。
この他にも、単発でいろいろなタイトルをつけた人は多いのですが、やはりある程度の追随者が出て認知されるというところがあって、曲種として確立されるところまではなかなかゆかないようです。
ざっと見てきても、ある程度確立された曲種が創始されたのは、前期ロマン派あたりが圧倒的に多いようです。後期ロマン派以降になると、一曲一曲にそれぞれのタイトルをつけた標題音楽が主流になって、「曲種」を創始しようというような気分ではなくなったのでしょう。
細かく見てゆくと、国による好みの差みたいなものもあるかもしれません。いずれまた考えてみたいと思います。
(2013.3.3.)
|