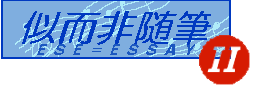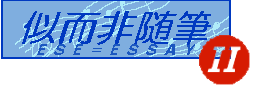|
「変奏曲」という名を持つ楽曲はたくさんあります。「ソナタ」に匹敵するくらいあるかもしれません。
そもそも「変奏(ヴァリエーション)」というのは音楽を作る上での基本的なテクニックのひとつであり、変奏曲と名づけられていない一般の作品の中でもごく普通に見受けられます。要するに同じモティーフないしフレーズを、さまざまな装飾をつけて変形して演奏するというのが変奏の本来のありかたです。
従って、記譜法がまだ未発達だったバロック時代頃までは、例えばリピート記号で繰り返す際に、演奏者が即興的に変奏を加えるというようなことはざらにおこなわれていました。例えば声楽ではダ・カーポ・アリアと言われるものがあり、第1部分と第2部分を続けて歌った後にもういちど第1部分を繰り返す構造を持っていますが、繰り返した第1部分では、楽譜に書かれていないいろんな装飾を、かなりきらびやかに付け加えて歌い手のノドを誇示するということが定石でした。バロック・オペラが一体にやたらと長いのは、アリアがほとんどこのダ・カーポ・アリアの形になっていたせいでもあります。のちにダ・カーポ・アリアは廃れましたが、ノドを誇示するための、繰り返しの即興装飾の部分はカデンツァとして残りました。
器楽でも同じようなことがおこなわれていましたが、作曲者が特に奏法を指定したい時には、ドゥーブルというものを付けることがよくありました。ドゥーブルとは英語で言えばダブルで、意味もまさに「重複」にほかなりません。もとの形を重複して別の装いにするということだったのでしょう。
複数のドゥーブルがつくこともあります。別にトリプル、クワドラプルなどと呼びかたが変わってゆくわけではなく、ドゥーブルI、ドゥーブルIIのように番号が添えられます。クープランの鍵盤楽器作品にもしばしば見られますが、ラモーのイ短調ガヴォットになるとドゥーブルが6つもつけられており、いまで言う変奏曲と少しも変わりません。「ガヴォットと変奏」というタイトルで演奏されることも多いようです。
これとは別に、フォリア、パッサカリア、シャコンヌなどと呼ばれる舞曲がありました。これらはいずれも3拍子のゆったりした舞曲で、相互に似ているところもあり、古い時代には区別があまりはっきりしていなかったようでもあります。どれも、低音に置かれた4小節ないし8小節の定型的な旋律が繰り返され、その都度高音部の対旋律が変化してゆくという形を持っています。同じフレーズが繰り返されるので退屈しそうですが、一種の輪舞のようなものだったようなので、踊る分にはそれで充分だったのでしょう。ただ音楽としては単調な繰り返しを避けるため、対旋律をかなり自由奔放に変えてゆくようになりました。
この中で、フォリアはもとの低音旋律そのものが決まっているため、あまり作曲家の興味を惹かなかったようです。リストの「スペイン狂詩曲」で聴くことができます。どこかで聴いたことのあるメロディだな、と思われたとすれば正解です。フォリアというのはあのメロディを使うに決まったものなのでした。
パッサカリアとシャコンヌは、作曲家の創意で低音旋律を作ることができたので、多くの作曲家がチャレンジしました。ただ、これも初期にはやや決まった形があったのかもしれません。ヘンデルのト長調シャコンヌを聴くと、低音の動きがバッハの「ゴールトベルク変奏曲」とそっくりなことに気がつきますが、あれがシャコンヌの本来の低音旋律だったのかもしれません。「ゴールトベルク変奏曲」はシャコンヌの技法で作られています。
ただバッハやヘンデルの頃になると、パッサカリアとシャコンヌの区別もわりとはっきりしてきました。パッサカリアは低音の「旋律」が繰り返されるもの、シャコンヌは低音にもとづく「和声」が繰り返されるものという趣きになって整理されたようです。パッサカリアよりはシャコンヌのほうがより自由度が高くなりそうですね。バッハのオルガンのためのパッサカリアと、無伴奏ヴァイオリンのためのシャコンヌとを較べてみると、その意味がわかりやすいと思います。
これらはその後あまり顧みられることがなくなりましたが、ブラームスはパッサカリアを2回使っています。『ハイドンの主題による変奏曲』の終曲と、交響曲第4番の第4楽章です。ただし『ハイドン変奏曲』のほうはもはや3拍子でも8小節でもなく、2/2拍子で、5小節のフレーズが繰り返されています。
私もパッサカリアを1回とシャコンヌを2回使いました。パッサカリアは『女声合唱のためのインヴェンション』の終曲に使っています。テキストにした立原道造の詩がきわめて短かったため、繰り返しフレーズにするのが良いと考えてのことでした。シャコンヌは高校生の時に書いた無伴奏ヴァイオリンのためのものがひとつ。これはお察しのとおりバッハに倣ったものですが、もうひとつはソナチネ第3番の第3楽章がシャコンヌになっています。全体がソナタであれば変奏曲にするところを、ソナチネですのでもうひとつこぢんまりとしたシャコンヌを採用したのでした。
さて、ドゥーブルの習慣と、パッサカリアやシャコンヌの伝統が統合されて、変奏曲が生まれたと考えて良さそうです。はっきりと「変奏曲」と名づけられた最初の作品が何であったのかはよくわかりませんが、最初の大きな成果はやはり「ゴールトベルク」でしょう。これがはじめての変奏曲と考えると、少々手が込みすぎているので、やはり先行作品がいくつもあったものと考えたい気がします。
「ゴールトベルク変奏曲」(原題は「30の変奏を持つアリア」)は上にも書いたとおり、シャコンヌの技法を応用して書かれています。ただし主題は32小節を持ち、シャコンヌの4倍の長さに拡張されています。
不眠症のお殿様を眠らせるために書かれたと言われるほどで、全部まともに弾くと1時間以上かかる長い曲ですが、当時の鍵盤楽器音楽のあらゆるテクニックを網羅するつもりで構成されたとも伝えられます。
3の倍数(ナベアツ?)番めの変奏には、最後の第30変奏を除いて、必ずカノンが置かれています。それも、最初の第3変奏は同度のカノン、次の第6変奏は2度のカノン、第9変奏は3度のカノン……と進んで行って、第27変奏は9度のカノンとなっています。なおかつ4度と5度は反行のカノン(上下を逆転させたカノン)になっており、その凝りようには唖然とさせられます。『音楽の捧げもの』と同様に、カノンのカタログにもなっていると言えるでしょう。
ヘンデルにも「変奏を持つアリア」があります。「調子の良い鍛冶屋」と愛称が付けられている曲が有名ですが、これはラモーなどのドゥーブルの延長上にある感じで、「ゴールトベルク」ほどの完成度はありません。「ゴールトベルク」はカノンの挿入だけではなく、長調と短調を入れ替える、拍子を変える、舞曲風にする、他の曲を引用するなど、実にさまざまなアイディアが盛り込まれています。同時代でぬきんでていたばかりではなく、後世にも、これを上回るほどにすばらしい変奏曲は稀かもしれません。
ハイドンやモーツァルトも変奏曲をたくさん書きましたが、旋律もしくは伴奏を変形するというステレオタイプにとどまっています。ただ、途中にひとつないしいくつか、違う調(多くは同主調──長調と短調の入れ替え──)を入れておくとか、ゆっくりしたテンポの変奏を入れておくとか、拍子を変えた変奏を入れておくとか、そういうことは普通におこなわれるようになりました。モーツァルトの「トルコ行進曲付き」ソナタの第1楽章を見るとわかりやすいのですが、イ長調、アンダンテ、6/8拍子の主題が、第3変奏でイ短調となり、第5変奏でアダージオとなり、第6変奏で4/4拍子になります。また有名な「きらきら星変奏曲」では、ハ長調、少し速め(テンポ表示は無い)、2/4拍子の主題が、第8変奏でハ短調に、第11変奏でアダージオに、第12変奏で3/4拍子になります。
変奏曲の歴史に劃期をもたらしたのは、やはりベートーヴェンでした。彼はハイドンやモーツァルト流の変奏曲もいくつも書いていますが、そういう作品にはあまり作品番号を与えていません。他人の作った曲を主題として用いることが多かったせいかもしれません。最初に番号を与えたのは作品34「自作主題による6つの変奏曲」でした。これは上記の「調性」「テンポ」「拍子」を、全部変奏ごとに変えてゆくという力業を見せた曲で、なるほど変奏曲として自信作だったのだろうとうなずけます。具体的に言うと、主題はヘ長調、アダージオ、2/4拍子なのですが、
第1変奏 ニ長調、アダージオ、2/4拍子(これだけは調以外主題と一緒)
第2変奏 変ロ長調、アレグロ・マ・ノン・トロッポ、6/8拍子
第3変奏 ト長調、アレグレット、2/2拍子
第4変奏 変ホ長調、テンポ・ディ・メヌエット、3/4拍子
第5変奏 ハ短調、行進曲(アレグレット)、2/4拍子
第6変奏 ヘ長調、アレグレット、6/8拍子(調だけ主題と一緒)
という、非常にバラバラなことになっています。まだ後年の「性格的変奏」には至っていませんが、とにかく「変奏曲」というものの可能性をいろいろ試してみようという意欲が感じられます。
次の作品35も「自作主題による15の変奏曲とフーガ(エロイカ変奏曲)」です。この曲の主題は、それ以前にコントルダンスとして作られ、このあとではバレエ音楽『プロメテウスの創造物』、そして交響曲第3番の終楽章でも使われたという、ベートーヴェンお気に入りのメロディです。この曲では、バッハに倣ったのか、シャコンヌの技法、つまり低音に置かれた主題をメインとして扱うということをはじめています。この低音主題を強調するために、「主題の低音による序奏」と称される、それ自体が変奏曲ともなっている序奏が置かれています。このアイディアは交響曲第3番にもほぼそのまま受け継がれています。
第6変奏では主題のメロディをそのままでハ短調(並行調)に和音を付け替えたりしています。第7変奏がカノンになっているのもバッハへのオマージュだったでしょうか(その後、変奏曲の中にひとつくらいカノン風なものを入れるのもはやりました)。第14変奏では変ホ短調(同主調)となり、第15変奏ではラルゴと非常に遅いテンポになります。ラストにフーガを置くのも、その後よくおこなわれるようになりましたが、この曲がたぶん最初です。フーガのあとに、実はもう2回ほどフルな形での変奏が置かれており、序奏と合わせると、本当は「15の変奏曲」ではなく、変奏が21あるとも見えるのでした。
そしてこの曲から、「性格的変奏」と呼ばれる変奏技法がお目見えします。低音にこだわったため、メロディのほうにはかなりのフリーハンドを得たことが大きな要因でしょう。主題のメロディにはあまり関係なく、冒頭のモティーフに与えた変奏の形を、主題の和声構造に従って展開してゆくというのが性格的変奏です。形が一貫しているのでその変奏の「キャラクター」がはっきりしやすいためそう呼ばれます。
このあとに書かれた「自作主題による32の変奏曲」は、バッハの無伴奏ヴァイオリンのシャコンヌにインスパイアされたらしき名曲なのですが、なぜか作品番号が与えられていません。変奏ひとつひとつが完結せずにどんどん続いてゆき、緊張感が失われることなく最後まで持ってゆくという構造を持っており、上記の性格的変奏がさらに徹底されてもいて、大変よくできた曲だと思うのですが、あるいはバッハの真似をしたという意識があったのでしょうか。
作品79の「自作主題による6つの変奏曲」は有名な「トルコ行進曲(ベートーヴェンのほう)」を主題に置いていますが、これはさほど新しいアイディアが盛り込まれた様子はなく、どちらかというと平凡な変奏曲であるように思えます。やはり作品番号70〜80番台あたりは、ベートーヴェンの「迷いの季節」であった模様です。
そして作品120がこれまた有名な「ディアベリのワルツによる33の変奏曲」となります。他人の作品を主題に置いた変奏曲に作品番号が与えられているのはこれだけです。ここまでくると本当に自由自在という趣きがあり、拍子もテンポもいいように変えられていますし、小節数にさえこだわっていないようです。また、33の変奏それぞれにタイトルをつけた人が居るというくらい各変奏の性格が鮮やかです。
以上のピアノ用変奏曲の遍歴を経て、「第九」に連なっていくようです。「第九」の第3楽章は自由な変奏を伴ったロンド形式ですし、第4楽章は変奏曲の考えかたを全面的に応用したカンタータとなっています。
ロマン派の時代にも多くの変奏曲が書かれていますが、とりたてて注目すべきものは案外と少数です。シューベルトやショパンの変奏曲は、華麗ではありますが、モーツァルトの域を出るものではありません。メンデルスゾーンの『厳粛な変奏曲』などはベートーヴェンに多くを学んだ形跡がありますが、これも新しい創意というほどのことは無さそうです。
その中で、シューマンの『交響的練習曲』はひとつの劃期をもたらしたと言えるかもしれません。変奏曲ではなく「練習曲」を名乗っているとおり、かなり自由奔放に主題を処理しています。
ブラームスは変奏曲をたくさん書いた作曲家で、初期の「シューマンの主題による」「自作主題による」「ハンガリー民謡による」変奏曲にはじまり、「ヘンデル」「ハイドン」「パガニーニ」と充実したラインナップを見せています。ただ、変奏技法そのものにはさほど新しさが感じられないような気もします。ベートーヴェンからシューマンに受け継がれた「性格的変奏」の技法を、ブラームスが「完成した」というところかもしれません。
変奏曲の概念そのものに挑戦したようなのが、フランクの『交響的変奏曲』です。シューマンの『交響的練習曲』と間違いやすいタイトルですが、こちらはピアノとオーケストラのための協奏曲的作品で、ぱっと聴いてもあまり変奏曲という感じがしません。ヴァリエーションという言葉を反射的に「変奏曲」と訳すのは間違いなのではないかと思えてくるような曲です。むしろ「交響的多様性」みたいに考えたほうが、この曲の場合には妥当ではないかと考えたりします。
20世紀にも変奏曲は書かれましたが、「ヴァリエーション」よりも「メタモルフォーゼ」というような言葉が好まれるようになったふしがあります。訳すとすれば「変容」でしょうか。「オーケストラのための変容」みたいなタイトルの曲はいろんな作曲家が書いています。
そんな中で、形としては古典的な変奏曲のスタイルを守りつつ、「ゴールトベルク変奏曲」に挑戦するようなきわめて理知的な構造と、現代音楽らしい響きを兼ね備えた作品として、ジェフスキーの「『不屈の民』変奏曲」を挙げておきたいと思います。主題はチリだったかの民衆歌で、これに36の変奏が続きますけれども、ポイントはこの36という数字です。36=6×6で、変奏6つずつが明らかに組になっているのです。1〜6、7〜12、13〜18というように組になって、それぞれの中では変奏の「スタイル」が共通しています。一方、1と7と13とか、2と8と14とか、それぞれの組の中で同じ位置にある番号では、変奏の「技法」が共通しています。
さらに、それぞれの組を締めくくる「6の倍数」の変奏では、それまでの5つでおこなわれてきたことを集約する形になっています。のみならず、最後の組である31〜36では、例えば31なら1・7・13・19・25、32なら2・8・14・20・26など、「縦」に見た場合の5つを集約しています。当然、最後の第36変奏では、それまでのすべての変奏がちょっとずつ回想されるという構成になっています。
それだけではありません。一体に無調なので聴いただけではわかりませんが、変奏の骨組みとなっている音が、最初の12の変奏と最後の12の変奏では、5度圏を上昇しながら「転調」しています。簡単に言えば、ニ短調の主題が、ニ短調〜イ短調〜ホ短調〜ロ短調〜という具合に変わってゆくわけです(実際には「短調」には聞こえませんが)。
「『不屈の民』変奏曲」の楽譜を見て、以上のことに気がついた時には、正直なところあっけにとられました。そして、ジェフスキーは「ゴールトベルク」に堂々挑戦したのだ、と直感したのでした。
(2014.3.29.)
|