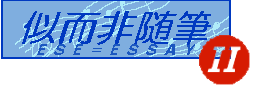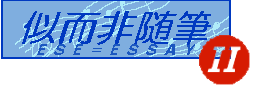|
フーガというのは言うまでもなくバロック時代を代表する曲種であるわけで、いちおう対位法音楽の頂点に位置するものとされています。模倣の技法を基本としつつ、相当に自由な処理が許されるため、1ページ内外で終わってしまう小品から、何百小節にも及ぶ大作まで作ることができるというのが魅力でしょう。
同じく模倣を基本としてはるかに厳格な様式を持つカノンは、厳格でありすぎるがゆえに、あまり大きなサイズのものを作るのは困難でした。ルネサンス期にはパレストリーナなどがカノンのみによって作られた大がかりなミサ曲を書いたりもしていますが、転調が限られてしまうのが欠点で、バロック期に入ると規模の小さな曲ばかりになってしまっています。その後もカノンは作られ続けていますが、作曲家の頭の体操みたいな試作や、ちょっとした輪唱みたいなものが多いようです。フランクのヴァイオリンソナタの終楽章はカノンを応用していますが、全面的にカノンというわけではなく、主要部分が完結したカノンになっていて、それが何度も現れるという形です。
カノンに較べると、フーガはずっと融通が利きます。
とりわけJ.S.バッハにとっては本質的な様式であって、大半の曲にフーガもしくはフーガ的な部分が含まれていますが、もちろんヘンデルにも多数のフーガがあり、その後の作曲家たちも積極的に採り入れています。
フーガ形式、という呼ばれかたをすることがありますが、フーガは主題の取り扱いかたのひとつの様式であり、複合三部形式とかソナタ形式のような、楽曲全体の組み立てを説明する言葉ではありません。構造自体は千差万別と言って良いでしょう。
フーガを説明する場合、いくつかの概念語を用いる必要があります。あまり他の形式では耳にしない用語です。
まず「主唱」。「主題」と言うこともありますが、英語で言うと「テーマtheme」ではなく「サブジェクトsubject」となります。全曲を支配統合する一連のフレーズで、長さはさまざまです。1小節足らずということもあれば、10小節近い大きさを持つこともあります。たいていの場合は、この「主唱」が冒頭に単旋律で歌われます。後述する「二重フーガ」などの場合は別ですが。
あるパートで「主唱」が終わると、続いて他のパートで「応唱」がはじまります。単に「応答」と言うこともあります。英語ではレスポンスresponseです。ただ、主唱が終わってもまだしばらく次のパートが出てこないこともあります。どこまでが主唱かということは、分析する場合はこのあとの展開を見て判断しなければならなかったりします。主唱が終わったあとで次のパートが出てくるまで続いている部分を「小結尾(コデッタcodetta)」と呼ぶこともあります。
さて、実は「応唱」の存在がフーガのキモとも言えます。カノンの場合、先行するパートを忠実に模倣するわけですが、フーガではここに「変応」という概念が導入されます。
「応唱」はまず、属調で導入されなければならないという原則があります。シャープのひとつ多い調性、またはフラットのひとつ少ない調性です。ハ長調のフーガならト長調で、ニ短調ならイ短調で入ります。
カノンでも、「5度の(厳格)カノン」という種類であればこの事情は同様なのですが、フーガの応唱にはもうひとつの原則があります。それは、
──主唱に含まれる主音を属音で、主唱に含まれる属音を主音で受ける。
というものです。ハ長調で言えば、主唱にドがあれば応唱ではソで受けることになり、これは属調(ト長調)である以上当然なのですが、問題は主唱にソが含まれた場合、応唱ではドで受けなければならないという点です。
属音というのはその調性の5番目の音ですが、ト長調の5番目の音はドではなくレです。厳格に模倣するならば、ハ長調の主唱のソは、応唱ではレになるべきです。ところが、ここをドにしなければならないために、形が若干変わってくることになります。これを「変応」というわけです。
また、応唱を属調からはじめるために、主唱そのものが主調から属調への転調を含んでいるということがあります。この場合、応唱では「属調→主調」という転調で答えなければならないということになっています。この時も変応が発生します。
ややこしいようですが、この変応によってフーガの多様性が生まれるとも言えるわけで、フーガを作成したり分析したりする上で必ず押さえておかなければならないポイントです。もちろん、変応を伴わない応唱もありますし、主唱中のすべての主音と属音を交換しなければならないというわけでもありません。主唱の中盤以降は変形されないということが多いようです。
さて、2番目に入るパートが応唱を歌うわけですが、この時最初に主唱を歌ったパートはどうしているかというと、応唱にうまくかぶさる対旋律を歌います。この対旋律はまったく自由であることもありますが、わりと固定的に扱われることもあり、その場合「対唱」という呼び方をします。英語だとカウンター・サブジェクトもしくはコントラ・サブジェクトです。前にちょっと書いた、受験用の「学習フーガ」では、必ず対唱を作らなければならないことになっていましたが、実際の曲を見ると別に必須ではありません。
3番目に入るパートは再び主調に戻り、主唱を歌います。この時、「対唱」がある曲であれば、さっき応唱を歌った2番目のパートが対唱を奏でることになります。当然ながら、「対唱」にも変応がおこなわれます。最初に入ったパートはここで「第二対唱」を歌う場合もありますが、たいていは自由なメロディに移ります。
古典的なフーガはパートの数が決まっていて、3声なら3つ、4声なら4つ以上の音が同時に鳴ることは滅多にありません。圧倒多数のフーガは3声か4声で、ごくたまに2声、5声などもありますが、まあ混声合唱に対応する4声というのが標準型と考えて良いでしょう。4声の場合は、4番目のパートが再び応唱を歌います。ここまでが「主題呈示部」と呼ばれたりします。ソナタ形式の呈示部とは少し意味が違います。
3声の場合の多く、あるいは4声であっても規模の大きな曲の時には、主題呈示部のあとに「対呈示部」というものが置かれることもあります。全パートが1度ずつ主唱を歌ったのち、もう1度か2度、主唱か応唱を繰り返すのです。いずれにしても、主調と属調を行ったり来たりしながら「調性感」を確立するのが主題呈示部や対呈示部の役割と言えます。
主唱が出てくるのはこれで終わりではありません。このあとも随所に主唱のメロディが聞こえてくるのがフーガの醍醐味です。
主題呈示部でひととおり主唱と応唱が奏されたあと、少し自由な部分(嬉遊部)が続いて、そのあと並行調に転調するのが普通です。シャープやフラットの数が同じで、長調と短調を入れ替えたものが並行調で、ハ長調ならイ短調、ニ短調ならヘ長調といった具合です。主唱も並行調に移されて演奏されます。並行調呈示部、あるいは第二呈示部などと呼ばれることもあります。並行調主唱も応唱を伴うことがあり、その場合はもちろん、「並行調の属調」ということになります。
また嬉遊部が置かれたあと、今度は下属調に転調します。シャープがひとつ少ない、またはフラットがひとつ多い調性で、ハ長調ならヘ長調、ニ短調ならト短調が下属調になります。
これまでの「主調→属調→並行調→下属調」という流れは、実はバロック音楽の基本的な調構造で、フーガでない曲でも、ある程度以上の規模を持つ時は、たいていこうなっています。バッハの組曲や協奏曲のたぐいを見てみるとわかりやすいと思います。
下属調でも主唱が歌われることが普通で、これも応唱を伴うことがあります。ただし下属調の応唱というのは下属調の属調、つまり主調になってしまうので、避けられることも少なくありません。代わりに、「下属調の並行調」で応唱ではなく主唱が歌われることもあります。学習フーガではこの「下属並行調主唱」も必須とされていますが、これも実際の曲を見れば無いことが珍しくありません。
以上、「主題呈示部」「並行調呈示部」「下属調呈示部」という3つの「呈示部」が出てきました。曲の規模や作曲者の創意で、もっと他の調に移ってゆくこともあり、ことにバッハ以降の作曲家たちはかなり自由に転調しています。「並行調呈示部」と「下属調呈示部」のいずれか一方を欠いている小規模なフーガを、「小フーガ」という意味でフゲッタと呼ぶことがあります。ソナタに対するソナチネみたいなものです。また最初の呈示部だけで、あとはまったく自由な流れになってしまうのを、「フーガ風」という意味でフガートと呼びます。フガートはそれ自体が独立した曲種になっていることはほとんど無く、例えばソナタの展開部をフガートで処理する、というような使われかたをする言葉です。
それぞれの呈示部をつなぐ部分を、上述したように嬉遊部(ディヴェルティメント)と言いますが、ここはまったく自由に(ただしパート数の範囲内で)作られます。学習フーガでは、主唱か対唱から「嬉遊句」なるものを抽出し、それを各パートに次々に置くことで嬉遊部を構成するということになっています。しかも主題呈示部と並行調呈示部のあいだの「第一嬉遊部」、並行調呈示部と下属調呈示部のあいだの「第二嬉遊部」、下属調呈示部のあとの「第三嬉遊部」にそれぞれ別の嬉遊句を用意しなければならず、なおかつ第一から第三へ向けて、嬉遊句も、嬉遊部全体も、だんだん長くしてゆかなければならない、という面倒くさい規則があるのですけれども、実際の曲ではそんなややこしいことにはなっていないことが多いようです。同じような嬉遊句を使ったり、その嬉遊句がそもそも主唱や対唱とは別に関係なかったり、学習フーガでは厳禁されている「反復進行」が平気で使われていたりします。長さもまちまちです。
大規模な曲になると、第三嬉遊部以降に、第二、第三の主題が登場することもあります。これらはそれ自体でまず主唱-応唱を形成し、時には他の調に移ったりもし、なおかつそのあとで本来の(第一の)主唱と組み合わせて登場したりします。こういう作りかたをしているのを二重フーガとか三重フーガとか呼びます。曲によっては第二の主題が冒頭から登場して、2声ではじまっていることもあります。
ちなみにバッハの『シンフォニア』(3声インヴェンション)の第9番は、ほぼ完全な姿を持つ三重フーガで、3つの主題が3つのパートにどういう組み合わせで配置されても違和感なく聞こえるように作られています。短いながら見事な作品です。
また、主題の反行型、拡大型、縮小型などが登場することもあります。反行型主題は上下を逆にした形で、バッハの作品でもしばしば使われ、わりと早い段階、例えば主題呈示部のすぐあとに出てくることもあります。ベートーヴェンは逆行型、つまり前後を逆にした主題も使ったことがありますが、こちらは滅多に実例を見つけられません。
フーガ独特の概念として、もうひとつ「追拍」(ストレット)というのがあります。これは主題のフレーズ全体を歌い終わる前に、次々と他のパートが追いかけてくるというものです。序盤から追拍が成されることもありますが、たいていは後半になってから、テンションを高める意味合いで置かれることが普通です。ただ、主題の形によっては追拍が作りづらいというものもあり、その場合は省略されることもあります。
学習フーガでは追拍についても細かい構成上の規則がありますが、もちろん実際の曲ではかなり自由に作られます。追拍によってテンションを上げ、クライマックスを経て終止に至るというのがフーガの定石です。最後にもう一度、完全な形の主唱が歌われることもありますが、無いこともあります。
フーガを構成しているのは以上の要素です。もちろん実際にはすべての要素が揃っていなければならないわけではなく、省略されるものもいろいろありますが、少なくとも「主唱」「応唱」の存在、並行調や下属調への転調などは備えている必要があります。
フーガは、上述したように、バッハにとっては楽想の本質的な形でした。『平均律曲集』や『フーガの技法』はもちろんですが、その他にも大量の「前奏曲とフーガ」「トッカータとフーガ」「幻想曲とフーガ」といったたぐいの作品があります。フーガと名付けられていないけれども明らかにフーガの応用というケースもあって、『イギリス組曲』の前奏曲などに見受けられます。
バッハ以降、楽想の本質がフーガ、という作曲家はあまり居なさそうです(故池内友次郎先生などはそうだったかもしれません)。そもそもバッハの晩年にはすでにフーガは時代遅れなものと見なされつつありました。バッハと同年であるドメニコ・スカルラッティがフーガをほとんど書いていないというのも注目すべきところです。「猫のフーガ」と称される曲(L.499)はありますが、フーガとして眺めた場合はきわめて変則的で、バッハのフーガと同列に論じるのは難しいかもしれません。
しかし、宗教音楽などではフーガ的な技法が使われ続けましたし、モーツァルトもベートーヴェンも後期作品に至ってフーガを好むようになりました。ベートーヴェンは19世紀という時代に適した形のフーガを作ろうと試みていたような形跡もあります。
シューベルトは「さすらい人幻想曲」の最後の部分をフーガっぽくしようとして失敗しています。ショパンに至っては少年時代に書いた習作が1曲残っているだけです。しかし、メンデルスゾーンやシューマンは、バッハの再発見をおこなっただけに、フーガもけっこうたくさん書いています。メンデルスゾーンのオルガンソナタや、シューマンの『バッハの名による6つのフーガ』などを見れば、彼らのフーガの作りかたがなかなか堂に入っていることを納得できると思います。
ブラームスもこの流れで語れそうな気がしますが、実のところブラームスにはフーガにおけるさほどの実績はありません。『ヘンデルの主題による変奏曲』の終曲に、ベートーヴェンの『エロイカ変奏曲』に倣ってフーガを置いていますが、あまり書法がこなれていないように思えます。シューマンの弟子ではありましたが、シューマンのポリフォニー好みをそのまま受け継いだようには見えません。
このあたりから、フーガを好む系譜はドイツ系を離れてフランス系に移る観があります。フランスの音楽学校で学習フーガがカリキュラム化された影響かもしれません。その嚆矢はやはりフランクでしょうか。代表的ピアノ作品である「前奏曲、コラール、フーガ」で、彼は近代的なフーガの扉を開いたと言って良いでしょう。サンサーンスやフォーレも、代表作というほどのものは無いにせよけっこうフーガを書いています。ラヴェルの『クープランの墓』の中のフーガは演奏される機会が多いですね。
その後は、ロシア(ソ連)に本場が移った感じです。なんと言ってもショスタコーヴィッチの、バッハの向こうを張った『24の前奏曲とフーガ』が燦然と輝いています。この段階になると、すでに機能和声は捨てられており、調性もわりとあいまいなものになっていますが、そういう響きの中でどういう形でフーガを作ってゆくべきだろうかという実験性が色濃くにじみ出ています。
ショスタコーヴィッチの第1番、ハ長調のフーガの楽譜を見て、私は「あ、やられた!」と思ったものでした。ひとつも臨時記号を使っていない、つまり完全に白鍵だけで書かれているフーガです。本来、転調が必須であるため、フーガに臨時記号が全然無いということはまずありえないのですが、ショスタコーヴィッチはあえて白鍵のみを使うことで、少しずつ変形してゆく主題を愉しんでいます。モダンな意味での「変応」と言っても良いでしょう。さほど長くないこのフーガの中で、白鍵だけで作られる7つの旋法(イオニア・ドリア・フリギア・リディア・ミクソリディア・エオリア・ロクリア)が全部使われているところも注目すべき点です。
カバレフスキーもだいぶフーガを書きました。この人の場合は教育的観点からの作曲が多いのですが、それだけに「そんなに難しくなく、しかもモダン」という方針で徹底しており、フーガもそういう作りかたをしています。
あと「現代的なフーガ」としてよく知られているのは、バーバーのピアノソナタの終楽章でしょうか。ちょっとカプースチンの先駆を成すような、シンコペーションを多用した、ハードジャズっぽい響きの作品になっています。この流れでは、ラウタヴァーラのピアノソナタ第2番の終楽章なども挙げられそうです。フーガという形式は、廃れそうでなかなか廃れない、芯の強さを持っているようです。
私は受験時代に学習フーガを山のように作らされましたが、意外と性に合っていたようで、その後もフーガっぽい曲はわりと書いています。学習フーガの祟り(?)で、ついいつも対唱を考えたり、嬉遊句を用意しておいたりする癖が抜けないのですが、もう少し自由に応用してみたいと思っています。
(2015.3.14.)
|