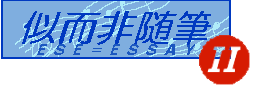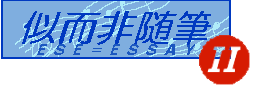|
土曜日は毎週ピアノ教室に教えに行っていますが、常に時間が詰まっているわけではありません。隔週の人も居て、1時間くらい空くこともあります。ひどい時には2時間まるまる空いてしまうこともあるのでした。
2時間空いている時は、教室の近くの書店へ立ち読みに行ったりすることもありますが、1時間だとそれほどの余裕は無く、だいたい教室の中で時間を潰しています。
持って行った本を読んでいることもありますが、楽譜を持って行ってピアノを弾いているということが多いようです。作曲の仕事が差し迫っている時には下書きを進めたりもしていますけれども。
楽器しか置いてない防音スタジオなので、他に気が散るものも無く、ある意味ではいちばん集中してピアノを弾ける時間と言えるかもしれません。私も決して熱心なピアノ弾きではなく、家では弾くことも少ないのですが、教室での待機時間は私としては貴重なプレイタイムなのでした。
その時によって、いろんな楽譜を持ってゆきますが、薄い本だとあっさり1冊弾き終えてしまったりします。ちょっと物足りなく思ってしまいます。
その点、ベートーヴェンのソナタアルバムなどを持ってゆけば、当分は愉しめます。何しろとんでもない分厚さです。分厚いので、持ち歩くには重くて不便なのですが、自転車の籠に載せてゆくだけなのであまり気になりません。電車と徒歩で通うのであれば少しイヤになりそうですけれども。
ベートーヴェンのピアノソナタは、子供の頃の習作や未完作を除いて、番号付きのものが32曲あります。ほぼ全生涯にわたって書かれており、ベートーヴェンの作風の変化をもっとも先鋭的な形で示しているので、ピアニストにとってのみならず、研究者や後続の作曲家にとっても、汲めども尽きぬ音楽の宝庫と言える存在です。
ピアニスト達からは、「ピアノの新約聖書」と呼ばれています。ちなみに旧約聖書と呼ばれているのはバッハの平均律曲集です。あとショパンの練習曲集がこの流れでなんとか呼ばれていたような気がしますが、よく憶えていません。
ピアニストたる者が必ず全曲を勉強しなければならないという意味合いでそう呼ばれているわけですが、コンサートレパートリーとしては最近あまりはやっていないのが少々残念です。ショパンやリスト、ドビュッシーといった華やかな曲ばかりが好まれて、「新約聖書」がおろそかにされるのは由々しきことですが、別の見かたをすれば、ベートーヴェンのソナタは勉強すればするほどその「怖さ」がわかってきて、うかつに手をつけられないという気分もあるのかもしれません。
亡くなった神野明先生は、ショパンとリストの演奏では日本人としては他の追随を許さないほどのピアニストでしたが、ある時丸一日スタジオにこもって、ベートーヴェンのソナタを全曲ぶっ通しで弾いてみたそうです。リサイタルやレコーディングなどで扱うつもりは毛頭無く、ただ自己満足のためだけにやったのだそうですが、
「いや、至福の時だったね」
と述懐しておられました。
「時間はどのくらいかかりました?」
私がそう訊ねると、
「10時間くらいかな」
10時間ベートーヴェンと対話し続け、いわば楽聖の生涯を俯瞰する体験を持ったのですから、なるほど至福の時だったろうと納得しました。
ベートーヴェンはピアノを管弦楽のように使った、とよく言われます。
先輩のハイドンやモーツァルト、あるいはシューマンなどがピアノを室内楽のように使った、あるいはショパンがピアノをピアノとしてのみ使ったというような言われかたと対比させてのことですが、確かにベートーヴェンのソナタにはシンフォニーの響きが裏打ちされていることを感じます。
ただし、オーケストラ作品においては、ベートーヴェンはピアノよりははるかに慎重でした。例えば交響曲第1番はだいたいピアノソナタ第11番と同じ頃に書かれていますが、それまでにピアノソナタにおいておこなっていたさまざまな「実験」を、交響曲ではあまり活かせていない印象があります。作風としては、交響曲第1番はピアノソナタで言えば4番から7番くらいの位置に相当するような気がします。年代としては数年ずれている感じです。
交響曲第5番(運命)はピアノソナタ第23番(熱情)とよく較べられますが、これも4年ばかり熱情ソナタのほうが先んじています。
それぞれのジャンルで最大の作品と言われるのが、交響曲第9番(合唱)とピアノソナタ第29番(ハンマークラヴィーア)で、このソナタについては私は大学のゼミで八村義夫先生の指導のもとかなり詳細に分析をおこないました。そして多くの点で「第九」と共通するものがあることを実感したのですが、これも作曲時期は第九よりも5年ほど早くなっています。
つまりベートーヴェンは、ピアノソナタで試してみた成果を、常に数年かけて交響曲に応用していたと考えられるのです。さきに「作風の変化をもっとも先鋭的な形で示している」と書いたのはその意味でした。
ちなみに八村先生は、きわめて前衛的な作風の作曲家として知られていましたが、ベートーヴェンのソナタに関してはものすごい勉強をされていました。いちど先生の持っていたベートーヴェンの楽譜を見せて貰いましたが、ページいっぱいに細かく書き込みがされ、ついにはそれで足りずに紙を継ぎ足してメモが書かれていました。同席していた先輩がたも度肝を抜かれていたようです。前衛とは、古典に背を向けることではなく、逆に古典をとことん検討しぬいた上で、はじめて花を咲かせることのできるものなのだということを教えられました。
前衛と言えば、ベートーヴェンも当時としてはとてつもない前衛であったのだろうと思います。
その後の作曲家たちが、ベートーヴェンを手本としてみずからの表現を磨いて行ったために、ベートーヴェンは「古典」の最たるものとなり、ある意味ではもっとも「あたりまえ」な存在になってしまった気配がありますが、とんでもないことです。私は年齢を重ねるに従って、その凄さをひしひしと感じるようになってきました。
例えば彼は、ピアノという楽器の進歩に合わせて、どんどん作風を変化させています。
彼の生きた18世紀末〜19世紀初頭は、ピアノという楽器もいわば烈しく変化した時代でした。端的に言うならば、はじめの頃のピアノは今のものとは音域が全然違います。初期のピアノは前身となったチェンバロなどと同じく、下1点Fから3点Fまで5オクターブ、61個の鍵盤しか持っていませんでした(最初にクリストフォリが作ったものはさらに少なく54鍵)。モーツァルトのピアノ曲にはこの音域を外れる音はひとつも出てきません。なおハイドンはもう2つ加えた3点Gまでのピアノを持っていたらしく、後期のピアノソナタにはその最高音を用いた曲もあります。
さて、ベートーヴェンの生きた時代と歩調を合わせるように、ピアノの音域が拡がります。1803年にはエラールが68鍵(下1点F〜4点C)のピアノを製作し、18年にはブロードウッドが73鍵(下1点C〜4点C)、24年にグラーフが78鍵(下1点C〜4点F)と、次々に音域を拡げてゆきました。現在の形の88鍵(下2点A〜5点C)となったのは19世紀後半のことであったようです。
1803年にエラールが作ったピアノは、早速ある貴族を通してベートーヴェンに贈られました。そして書いたのがピアノソナタ第21番(ヴァルトシュタイン)です。この曲は、新しい音域を得て嬉しくて仕方がないかのように、高音域がこれでもかというくらい頻出します。新型のピアノの演奏可能性を、とことんまで試してみたという趣きがあります。
これは、今で言うならば新機能満載のシンセサイザーを入手して、たちまちのうちにその新機能をすべて活かしきった作品を書いたようなもので、ベートーヴェンがいかに進取の気性に富んでいたかがよくわかります。
ハンマークラヴィーアソナタも、ブロードウッドから新型のピアノを贈呈されたのに感激して書いたと言われていますが、上記の73鍵ピアノの開発よりは少し前のようですから、これは音域の拡張でなく、おそらく機構の改良がされたピアノだったのでしょう。ピアノの歴史のその頃の年代を見ると、フレームの鉄製化がそれにあたるようでもあります。また、このソナタの譜面に、それまで見られなかった左ペダル(ソフトペダル)の指示が出てくることを考えると、左ペダルの使用がやりやすくなったピアノだったとも考えられます。とにかくこの場合も、ベートーヴェンは新型ピアノの機能を最大限引き出そうと努めていることがわかります。当時の彼はすでにかなり耳疾が進み、音がほとんど聞こえなくなっていたはずですが、新しいソフトペダルの音色などまでしっかり考慮した曲を書いていたのには驚かされます。
ピアノに新しい工夫が加えられると、ベートーヴェンがすぐにその工夫を活かした曲を作ってくれるのですから、当時のピアノ製造業者たちも張り合いがあったことでしょう。この時代の急速なピアノの進歩は、ベートーヴェンによって支えられるところも大きかったはずです。
ピアノという楽器に対する進取性だけではありません。ベートーヴェンの前衛性は、より本質的には楽曲構造にあらわれています。
私が若い頃に気がついていまだに驚いているのは、ベートーヴェンのピアノソナタが、第1番からして4楽章を持って作られていたことです。
なぜ驚くかわかりづらいかもしれませんが、ハイドンもモーツァルトも、ピアノソナタで4楽章を持つものをほぼ1曲も書いていないという事実を述べれば、その異常性がわかると思います。クレメンティに至って、ようやく後期にわずかながら見ることができます。
要するにピアノソナタというのは、3楽章制が普通だったのでした。この事情は、現在でも協奏曲は3楽章制であるというのと似ています。ベートーヴェンが出現しなかったら、ピアノソナタも3楽章が主流だったでしょう。それを一躍、4楽章にしたのがベートーヴェンでした。
似たような構造を持つ楽曲として、交響曲とか弦楽四重奏曲とかは、ハイドン時代から4楽章を持つものが主流でした。つまり、ベートーヴェンはそもそもの最初から、ピアノソナタを交響曲や弦楽四重奏曲に比肩するものとして考えていたことがわかります。
もっとも、4楽章を備えたピアノソナタは、32曲中10曲ですので、多数派とは言えません。終楽章の前にかなり長大な序奏(というより序曲)を伴った3楽章、いわば準4楽章のものを含めても13曲です。それでも、ベートーヴェンに続く作曲家たちは、ソナタと言えば基本は4楽章制……という考えかたで作るようになりました。3楽章以下の場合、4楽章制の中のどれかが省略もしくは統合されたものとして考えることが多いようです。
基本構造は、ソナタ形式を持つ第一楽章、ゆったりした第二楽章、メヌエットの第三楽章、華やかなフィナーレである第四楽章というもので、これはモーツァルト以前の交響曲や弦楽四重奏曲と同じです。ただし、ベートーヴェンは第1番のソナタはこの通りに作りましたが、第2番では早くもメヌエットをスケルツォに差し替え、以後スケルツォのほうが主流となりました。
ソナタ形式と言えばベートーヴェンにとって本質的な楽曲形式でしたが、それでも第12番、第13番では「ソナタ形式を用いないソナタ」という新機軸を打ち出しています。まあ、それ自体はハイドンやモーツァルトもやったことがありますし、ベートーヴェンもその後はあまりやっていない(第22番あたりに見られるくらい)とはいえ、自分が作り出した定型すらも常に壊して新しいものを探究し続けた人であることは確かと言わざるを得ません。なお、第12番ではスケルツォを第2楽章に置くという実験もやっており、これはハンマークラヴィーアソナタ、そして「第九」に受け継がれます。その後の作曲家はむしろこちらを主流とし、ショパンの3曲のソナタもすべてこの形になっていますし、20世紀のバーバーのピアノソナタもそうなっています。
ソナタ形式に対しての工夫の数々は、ここに述べるには厖大すぎて、一冊の本が書けるくらいなので省略しますが、フィナーレによく置かれるロンドにも彼はいろいろ工夫をこらしています。特に、ソナタ形式とのハイブリッドとも言えるロンドソナタ形式は、それまでの作曲家には見られなかった構造です。実のところロンドソナタ形式というものへの理解は、私自身も意外と遅くまで届いていませんでした。ロンドソナタ形式のつもりで書いた曲が、実はただのロンド形式に過ぎなかったというお粗末な経験もあります。
ソナタの中に本格的なフーガを導入するという試みは晩年になっておこなわれました。ハンマークラヴィーアソナタ、そして第31番にフーガが採り入れられていますが、第28番の終楽章、第30番の終楽章(変奏曲)の第5変奏、第32番の第一楽章など、後期のピアノソナタには随所にフーガ的な考えかたがちりばめられています。モーツァルトも最晩年に至って、ソナタや交響曲にフーガの考えかたを導入しましたが、ベートーヴェンはより徹底したと言えるでしょう。フーガというよりもっと広い、ポリフォニックな処理ということであればもっと初期の頃からやっています。
楽曲の和音構造についても、新しい試みを次々とおこなっています。
ピアノソナタ第16番から第18番は、「作品31」としてまとめて発表されましたが、これが出た時に度肝を抜かれた人は多かったのではないかと思います。第16番はともかくとして、第17番(テンペスト)は属和音(ドミナント)の第一転回型という響きから始まります。これは実に画期的なことで、曲のアタマというものは主和音(トニック)で始まるに決まったものでした。モーツァルトには若干、主和音でない和音から始まる曲もありますが、それにしてもソナタや交響曲の第一楽章を属和音ではじめるという大胆さは見られません。さらに続く第18番は、さらに斬新なことに下属和音(サブドミナント)から開始されるのです。この人はどこまで行くのだろう、と当時の人々は思ったのではありますまいか。
繰り返しになりますが、こうしたことはその後の作曲家たちによって模倣されたり変容されたりしておりますので、今となってはそんなにびっくりするようなことではありません。しかし、当時はおそらく一作ごとに人々を驚かせていたに違いないのです。ベートーヴェンは、非常に貪欲に「新しい表現」を求め続けた人でした。現代のもっとも先鋭的な作曲家でも、彼以上に貪欲であるかどうかは疑わしいと思います。本当の前衛は、次代の古典となりうるものなのです。
ベートーヴェンのソナタアルバムを弾き直すたびに、いろいろな発見があるのは驚くほどです。
おそらくベートーヴェンだけを見ていてはそういう発見はなかなか得られないかもしれません。同時代を生きたハイドン、モーツァルト、クレメンティなどの作品を見た上で、彼らがやっていなくてベートーヴェンがやっていることを探してみれば、その斬新さがよくわかるというものです。また、彼より下の世代にもかかわらず、彼と前後して世を去っているヴェーバーやシューベルトと見較べてみるのも興味深いでしょう。音楽史上の古典派とロマン派がどう違って、どう受け継がれたものであるのかも、そのあたりから見えてくると思われます。
古典中の古典であると同時に、今なお新鮮な発見に満ちている……やはり「新約聖書」のあだ名は伊達ではないと実感します。
なお、ベートーヴェンのピアノソナタ各曲についての考察も書きました。「ベートーヴェンのピアノソナタ・その飽くなき探究心」という稿をご覧ください。
(2012.12.8.)
|