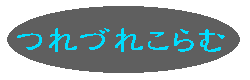
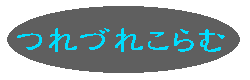
| この物語に登場する人名や役職名は、おおむね作者がでっち上げた架空のものです。女王(ひみこ)はまあともかくとして、宰相(みまし)にしても将軍(いこま)にしても、魏志倭人伝の「弥馬升」「伊支馬」という表記に基づいてはおりますが、それぞれが宰相職、将軍職であったという証拠はどこにもなく、役割そのものはフィクションです。 しかし、「夷守(ひなもり)」という役職だけは、根拠があります。 魏志倭人伝によると、対馬国、一支国(壱岐)、奴国(博多近辺)、不弥国(宇美?)の4国について、 ――官(大官)を**といい、副を卑奴母離という。 という記述があります。「官」の名前はそれぞれ違うのですが、「副」の方は実に4箇所に同じ名前の人物がいることになります。 どうやら、卑奴母離なる各国の副官も、個人の名前ではなく、そういう役職らしい。 卑奴母離は「ひなもり」と読むしかありません。「ひな」は鄙、つまり辺境であり、「もり」は「守り」に違いありません。それで小説では「夷守」の字を宛てました。 トップは国によってまちまちなのに、サブは共通となると、このサブは邪馬台国から派遣されていたお目付役だったのではないかと思われます。 つまり、30国あまりの国々が、合議の上で卑弥呼を立てて彼女の統治に服することにしたわけですが、その時のもとの国々の王がトップとなり、その下に卑弥呼直属の官僚が配属されたのでしょう。4国だけではなく、おそらくほとんどの国に配属されていたものと思われます。そして多分、もとの王たちは国の民衆の精神的支柱となり、祭祀を司り、実際の政務はこの官僚たちが執り行ったと見ても、それほど間違ってはいないと考えます。 キリストが活躍した頃、パレスティナの地を、土着のユダヤ王であるヘロデが支配しつつ、ローマ帝国から派遣された総督ポンティウス・ピラトゥスがお目付役となって実際の権力を握っていたことが連想されます。 ヘロデに相当する土着の首長には、「国守(くにつかみ)」という名を付けました。「くにつかみ」というのは「あまつかみ」に対応する言葉で、天孫族の神々に征服された各地の神様のことですが、その本来は、各地の首長を意味したに違いないと考えるからです。当時、首長と神様はそれほど差があるものとも思われていなかったでしょう。 邪馬台国の統治が非常に巧みだと思うのは、ピラトゥスに相当する総督職、あるいはお目付役を、各地の首長の上に置かず、「副」としてつけたことです。これなら、それぞれの国の人民も、邪馬台国に支配されているという意識をあまり持たずに済むでしょう。 いちばん上に権威の源泉としての首長を置き、その下の者が権限を握って実際に政務を動かしてゆく……考えてみれば、邪馬台国自体がそういう体制をとっています。 そして、この方法は、日本史において長く引き継がれてゆくことになります。 権威の源泉としての天皇を常に最高位に置きながら、蘇我氏、藤原氏、平氏、源氏、北条氏、足利氏、徳川氏といった実力者たちが権力を握る。権力者は次々と交代しますが、天皇は決して断絶も交代もしない。また一方、どれほどの力を手にした者も、天皇の権威によって認証されなければ、決して人々に天下人とは認められない。 普通、どこの王朝の国王も皇帝も、権威と権力を一身にまとおうとします。絶対者として国民に君臨し、支配しようとするのが当然です。 しかし、日本人は有史以来、この種の絶対者の存在を許しませんでした。蘇我入鹿、平清盛、後鳥羽天皇、後醍醐天皇、織田信長……権威の源泉をわが身にまとおうとした権力者も、権力を掌握しようとした天皇も、いつも誰かにストップをかけられました。 実は、権威と権限の分離は、組織を長期間安定させる秘訣と言われています。しかしどうしても、両方を兼ね備えたいというのが人情で、なかなかうまくゆくものではありません。ヨーロッパでこれが成功したのは、ようやく1688年、英国の名誉革命以降のことです。中国ではいまだに成功していません。 それを、日本人はおそらく3世紀からやっていることになります。文中のキムカが、そんなこと(権威と権限の分離)は半島でも大陸でもやっていないと、馬鹿にしたようなことを言っていますが、このシステムこそ日本人のたぐいまれな叡知であったと、私は信じています。 ただ、他と違うと言われるとうろたえるのが日本人でもあり、この卓越したシステムを、遅れたものとして嫌悪する、ツナビコのような連中も、結構いたかもしれません。 |