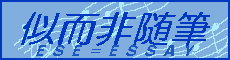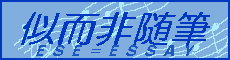|
国産オペラの話をしようというのではない。日本におけるオペラの上演について書くつもりである。
日本の演奏会は高い。なかんづくオペラの入場券となると、平気で万単位のチケットが飛び交う。貧乏人には手が出ない。それが結局、オペラというと何やら高尚そうなイメージということになり、庶民から敬遠されることにつながってしまう。
しかし、オペラというのはそういうものではない。アメリカでテレビの昼メロのことをソープ・オペラというが、本来その程度の語感と思ってよいのである。
今日のように映画やテレビが普及するまでは、観劇というのは民衆の普通の娯楽であった。オペラだって同じことで、そんなに襟を正して見るようなものではなかった。
携帯双眼鏡のオペラ・グラスというのがあるが、あれは本来、どういう風に使ったかご存じですか。舞台をより大写しで見るために持っていたのではない。双眼鏡を使わなければ舞台がよく見えないほどの巨大な劇場は昔はなかった。
実はオペラ・グラスは、客席に知人が来ていないか探すために使われたのである。知った顔を見つければ、次の幕間で声をかける。あるいは、美女を見つけてナンパする用途にも使われたであろう。
舞台そっちのけで、客席ばかり見回している客も少なくなかったと思われる。ボックス席などではもっとひどく、ワインと弁当を開けて談笑しているご婦人方も多かったようだ。
オペラというのはそういう場であり、それで文句を言う人はいなかった。
ロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティ等々といったイタリアオペラの作曲家たちは、現代で言えば映画音楽やテレビ音楽の作家に相当する。よくああ次々と書きとばせたものだと思うが、例えばベートーヴェンが交響曲を作る時のような、苦渋に満ちた顔はしていなかっただろう。
彼らの作品を見ると、決めの部分は見事なまでにワンパターンである。歌手ののどを誇示するためのアクロバティックなカデンツァ、そして走句を経てフィニッシュへ。「ロッシーニのアリアの最後の部分」だったら私だって今すぐにでも真似して作れる。
ロッシーニが締め切りに追われて、他のオペラで使った序曲をそのまま流用してしまったという話があるが、こういう融通が利くあたりも、どちらかというと今日の軽音楽に近い捉えられ方をしていたからであろう。
ヴェルディも前半は似たようなものだ。しかし彼と同年のドイツの作曲家ヴァーグナーが、オペラを交響曲のように作るという新機軸を打ち出し、これを楽劇(ムジークドラマ)と名付けた。どういうことかというと、それぞれの登場人物を、交響曲における主題のように扱い、例えばその人物が出てくるときには必ずある決まったフレーズ(固定動機──ライトモティーフ)かその変奏が流れる、というような作り方をしたのである。また従来のオペラのように、アリアごとにいちいちフィニッシュをつけて物語の流れを中断させることを廃し、あたかもひとつの幕が交響曲のひとつの楽章であるかのように、蜿蜒と切れ目なく音楽を続けさせた(無限旋律)。
ヴァーグナーのこの作曲法は、観客の方にも、交響曲を聴く時のような細心さを要求するものだった。切れ目がないので、よそ見やおしゃべりをしていてはわけがわからなくなる。固定動機を聴きのがすと意味不明になってしまう。観客は静粛にして、舞台に集中していなければならない。
言ってみれば、オペラを「芸術作品」に仕立て上げてしまったのがヴァーグナーであって、これ以後、あだやおろそかな気持ちでオペラを見るわけにはゆかなくなってしまった。
ヴェルディの後期は、このヴァーグナーの影響を受けているので、かなり肩の凝る作品となっている。
日本にオペラが導入されたのはヴァーグナー以後のことなので、どうしても、正装して微動だにせずに客席におさまっていなければならないような気がしてしまう。時々反撥が生じて、浅草オペラみたいなぶっちゃけたものが生まれたりもするが、あまり長続きしない。
まあそれはそれで仕方がないとしよう。好むと好まざるとにかかわらず、ヴァーグナー以後のオペラはそういうものになってしまったのだ。外国だってそれは同様である。ましてや映画やテレビが普及した現代、オペラが「ちょっとよそ行きの場」みたいな高級感を売りにするのは、それなりに理解できる。
私がここで論じたいのは、日本のオペラの興行形態なのである。
オペラ制作にはお金がかかる。衣裳、大道具、小道具、照明、オーケストラ等々、500万や1000万の金は易々と飛んでしまう。
入場料でそれを回収しようと思えば、高くならざるを得ない。500万円かけてひとつ公演を打つことを考えてみよう。断っておくが予算500万円というのはすこぶるチープな舞台である。
ホールはとりあえず1200人くらい入るものとする。一晩で赤字が出ないようにするためには、全席埋まったとしても入場料を平均4200円くらいにしておかないと追いつかない。招待や空席を考慮に入れれば、S席1万円、A席7000円、B席4000円といった設定(しかもB席は少ない!)にならざるを得ない。いくらかなりとも収益を上げようとすれば、さらに高くしなければならない。
この値段では、普通の庶民にとってはいささか抵抗を覚える。足が遠ざかるのも無理はない。
日本では、二期会公演などを見ても、ひとつの演目を上演しているのはせいぜい3日か4日間に過ぎない。これは実に短い。劇団四季のミュージカルが、数ヶ月から数年に及ぶロングランを重ねているのに較べて、あまりといえばあまりな短さである。
お金と手間をかけて作られた大道具が、ほんの数日であっさり解体されるのを見るのは、なんだか情けない気分にさせられる。
せめて一ヶ月くらいやるわけにはゆかないものか。
日本は人件費が高いので、一晩500万円の舞台を一ヶ月続ければそれでは済まなくなるのは当然だが、30倍ということにはならない。もちろん入場者の方も30倍ということにはならないだろうが、一ヶ月もやっていれば2度3度と見に来る人が必ず出てくる。さらによい舞台ならば口コミでも評判が広まるし、数日の公演では予定が合わなくて見られなくても、一ヶ月もあれば都合をつけてやって来る人だってたくさん居るはずである。
そうすれば入場料は下げられる。多売をすれば、単価が下げられるというのは、経済の常識ではないか。
多売をするほどの需要があるのかということになるが、これはあの手この手で需要を喚起しなければならない。
一ヶ月ではホール代だけでも馬鹿にならない、という反論があるかもしれない。
だが、考えてみて欲しい。昨今、地方へ出かけてゆくと、田んぼの中に、おそろしく立派なホールが建っているのをよく見かける。バブル期に、あちこちの自治体が競ってぶっ建てたのである。
が、ハコだけ作っても、肝心の中身がない。東京の一流ホールに匹敵する設備と規模を持つホールが、月に3回か4回、それもピアノ教室の発表会程度で使われていたりする。実にもったいない。
こういうところは、補助金を出してでも使って貰いたがっていたりする。ホールというものは、建てればいいというものではなく、メンテナンスにもかなりの金がかかる。なんにもしなくても維持費が飛んでいってしまうのである。多少補助金を出しても、使って貰った方がよほど助かるのである。
そんなホールなら、会場費は低く抑えられる。田舎なら人件費も比較的安い。
そんなところで公演を打って、客が来るものか、とお思いだろうが。
それは、やり方次第であると私は考えている。
制作関係者と、地方自治体、さらにできれば地元住民が、充分にその気になれば、成功すると思う。
私の夢想を語ろう。あちこちの町で、得意種目を作っておくのだ。あれもこれもやろうとしては失敗する。「何月にどこの町へ行けば、これこれが必ず見られる」という状態を作らなければならない。「これこれ」は「アイーダ」というような具体的な演目にしてもよいし、「プッチーニのオペラ」ということでもよい。あるいはオペラに限らず、歌舞伎でもミュージカルでもサーカスでもなんでもよろしい。
「この演目を見るなら、どこそこの町へ行け!」ということにするのだ。
バイロイトという町は、人口も少なく、他に大して取り柄もない寒村だが、シーズンになればヴァーグナーが必ず見られるというので、世界中から人が集まるのである。ヴァーグナーはこの町の議会を舌先三寸で言いくるめ、自分の作品だけのための劇場を建てさせたのであった。ヴァーグナーしかやらないけれど、ヴァーグナーなら必ずやっているのである。
もちろん、自治体側も、訪れる客のために最大限の便宜を図らなければならない。最寄りの駅から直通バスを走らせる、周りに廉価な宿泊施設を整備しておく、など。JRとタイアップして、都会からの割引往復切符などを発行してもよい。
毎年同じようなことをやるのだから、関係者の手順も馴れてくるし、大道具も何年も使える。とにかく制作費が、長い目で見るとどんどん安く抑えられるのである。その分宣伝や人的資源の開発に向ければ、さらに良質のものが出来上がる。
歌手やオーケストラの生活も安定する。一ヶ月ひとところで腰を据えて仕事ができるとなれば、稽古にも身が入る。イタリアなどでは、シーズン中の一ヶ月だけ、ただひとつの役だけこなし、あとの11ヶ月は遊んで過ごしているような歌手もいるが、本当はそれが理想である。日本の演奏家は忙しすぎるのだ。
こうして、定番的な演目はどんどん地方都市に任せてしまう。東京では何をやるかというと、一ヶ月もやっていてもとても客が集まりそうもない、実験的なもの、あるいは無名の連中のものなどを主に扱うようにするのだ。
地方で育った人が東京に進出するのではなく、東京で育った人が地方の名のある舞台に立つ、ような形にしなくてはならない。文化振興と地域振興を兼ねた一石二鳥の秘策である。
夏になると、草津や野辺山で音楽祭があって、それなりに人が集まっているが、音楽祭では目先がちらちらしすぎる。やはり同じ演目を一定期間やるべきである。
以上が私の夢想なのだが、いくつかの自治体が本気で考えてくれれば、決して夢物語ではない。
いろんなことをやろうとするな、専門特化した目玉を作れ、である。
どこか、考えてくれるところはないものか。
(1999.11.5.)
|