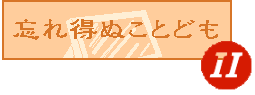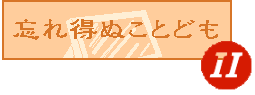|
「日本におけるキュビスム──ピカソ・インパクト」という美術展を見に、埼玉県立近代美術館まで行ってきました。
もう30年ばかり埼玉県民をやっていますが、この美術館に足を運ぶのははじめてのことです。最寄り駅は北浦和で、西口を出るとほとんど真正面に鬱蒼と樹が茂った公園が見えます。美術館はその公園の中にあり、下車徒歩5分とはかかりません。
私の家の最寄り駅である川口から北浦和はせいぜい京浜東北線の電車で13分程度ですから、30分あれば充分行くことができる近さです。こんな便の良いところにある美術館に、なぜ今まで行くことがなかったのだろうかと不思議に思うほどでした。
たぶん、美術館とか博物館とかなら東京のほう、という無意識の思い込みがあったのでしょう。実際、都内でも有数のミュージアム密集地区である上野までも、うちからなら30分ちょいで行くことができますので。
今日出かけたのは、前の週に発表会があったために、生徒のレッスンを休みにしていたマダムに誘われてのことでした。マダムはいろいろと行きたい美術展があったらしく、その中に「日本におけるキュビスム」展も含まれてはいたのですけれども、東京と反対側である北浦和に行くにあたって、マダムも一瞬
「え〜?」
という顔をしました。都内の催しに行くつもりになっていたのかもしれません。
ともあれ午後になってから美術館に出かけました。
キュビスムというのはむろん、20世紀初頭にピカソやブラックらによって確立された美術思潮で、立体派と訳されたりもしました。私もさほど詳しいわけではありませんが、立体である対象を描くにあたって、できるだけ多くの面を、つまり一方向だけからでは見えないような面までも、1枚のキャンバスの上に表現しようとする試みというのが本来の狙いだったのだろうと理解しています。
その前史として、たぶんセザンヌが提唱した方法、対象を立方体や球、円錐などの幾何学的な要素に分解して把握するという技法がベースになっているのでしょう。セザンヌ自身の作品にも、普通に見ただけでは絶対に視界に入らないはずのものが描かれているというのがあります。その技法を敷衍してゆくと、対象の正面と側面を同時に描くというキュビスムの基本的な概念に結びついてゆくのも納得できます。
実際には見えない角度のものを同一平面上に描くわけですから、当然デフォルメが加わることになります。そのデフォルメの奇妙さを愉しむというのが、キュビスムの持つ本来の意味合いであったでしょう。
美術展のアオリ文句によれば、日本の絵画は歴史上2回、キュビスムの洗礼を受けることになったというのでした。
第1回目は明治末期から大正初期にかけて、ほぼキュビスム自体が誕生して間もない頃のこと。萬鐵五郎や東郷青児、坂田一男などが、ヨーロッパの新しい美術思潮としてキュビスムに接し、その影響を受けた絵を描いたようです。ただ、このときは言ってみれば「ちょっと試してみた」くらいのことで、足を踏み入れた画家たちにしても、その後の作品でキュビスムを究めてゆくという方向へは進まなかったとされます。日本の画壇ではむしろフォーヴィスムやシュールレアリスムなどのほうがもてはやされたようです。
それが一変したのは、戦後わりとすぐの昭和26年、東京と大阪で開かれたピカソ展が契機であったとのこと。画壇にはまさに衝撃が走り、われもわれもとキュビスム──というよりピカソっぽい絵を描く画家が急増したらしい。これが第2回の洗礼で、この展覧会ではそれをピカソ・インパクトと呼んでいるわけなのでした。
ピカソに限らず、どうも日本の画壇というのは、「欧米ではいま、これがはやりだ」となると、誰も彼もがなだれを打つように同じような傾向の絵を描き始め、その流行に乗れなかったり背を向けたりしたような作品に対しては、まるで一顧だにせず評価しないようなところがあるような気がしてなりません。さすがに近年ではそんなことはないのかもしれませんが、少なくとも昭和のある時期までは確かにそうした空気が存在していたのではないでしょうか。去年鴨居玲の作品展を観に行ったときにも触れましたが、戦後しばらくなど、
──抽象画にあらざるものは絵画芸術にあらず。
というような空気があったようです。鴨居玲もその空気に逆らえず抽象画を描いてみたものの、あまり性に合わず、といって具象画を描いていても日本に居ては評価されないため、息苦しくなって南米に逃げ出したのでした。同じような息苦しさを感じていた画家も少なくなかったことでしょう。
もっともそれは画壇だけのことではないかもしれません。文壇でも楽壇でも似たようなところはありそうです。たとえば私の畑である作曲の世界でも、しばらく前までは、
──無調にあらざるものは現代の音楽にあらず。
というような空気がありました。私の学生時代、
「いやあ、久しぶりに『現代曲』を書いたよ」
「そうか、おれはここしばらく書いてないな」
などという会話が普通に交わされていましたが、この「現代曲」とは何かと言えば、煎じ詰めれば「無調の音楽」ということに過ぎませんでした。それほどに「無調=現代」という思い込みが強かったのです。
ちなみに音楽のほうでも、ピカソ・インパクトと似た現象がありました。1970年の大阪万博のドイツ館で、シュトックハウゼンの「シュピラール」が繰り返し演奏されていたのですが、これが日本の音楽家たちにとって大変なインパクトであったようです。それまで「これこそ現代音楽」というような顔でもてはやされていた十二音技法など、このときを境にすっかり息をひそめてしまいました。
しかし、表現者として、すぐ「流行に乗る」というのはいかがなものでしょうか。
「わが道をゆく」のはなかなか苦しいものです。ときには周囲からの酷評、冷笑、無視という仕打ちに堪えなければなりません。流行の方式に乗っかったほうがずっと楽です。
従来、先覚者として新しい表現を開拓した者が、旧套な保守派からそういう仕打ちを受けるものだと思われていたふしがあります。けれども、20世紀に入ってからは、むしろ逆で、「進歩的」な流行に乗っかることこそが正義であり、それを受け容れられないほうが、反動とか旧弊とか呼ばれて軽蔑されるような風潮になっていました。
これは別に日本だけの話ではありませんが、日本ではとりわけそういう空気が強かったように思えます。
「鑑賞者」が時代時代の流行を追い求めるのは仕方がありませんが、「表現者」が流行に軽々しく乗ってゆくのは、どうもあまりカッコ良いことではないように思うのですが、いかがなものでしょう。
さて、1910年代から20年代あたりにかけての第一次キュビスム受容期、50年代における第二次受容期という具合に、展覧会では分けて展示されていました。
展示側の評価としては、第一次受容期では一種の「スタイル」としてキュビスムを採り入れたものの、フォーヴィスムやシュールレアリスムに較べると表面的な受容にとどまって、キュビスムそのものを掘り下げようとする画家は少なかった……という趣旨であったようです。
それがピカソ・インパクトを経た第二次受容期では、もっと本質的なところまで影響を受けたのだと言いたいらしいのでした。
その評価が当を得ているのかどうか、わが国の西洋美術史に疎い私にはよくわかりませんが、素人目から見ると、第二次受容期の絵は、どれもこれもピカソの亜流みたいな印象を受けたのも事実です。「ゲルニカ」そっくりの手法で描かれた群像画がありました。ピカソの好んだミノタウロスモティーフをパクったとしか思えない女性と牛の絵もありました。こういう作品を「本質的なところまで影響を受けた」と言えるものなのでしょうか。
──こういう絵が受けるらしい。
というので描いたに過ぎないのではないか、という危惧が拭えません。
むしろ第一次受容期の画家たちのほうが、自分自身の作風の中にキュビスム的要素をうまく取り込んでいるように私には思えました。東郷青児なんかはこのキュビスム影響期のあとで、一種独特の美人画を描き続けることになるわけですが、キュビスムを志した経験は決して後年の作品にとって無駄になってはいないと思います。
展示の記事の筆者は、第一次受容期の画家たちが、他の思潮にもいろいろ染まって、キュビスムを究めてゆかなかったことがいくぶん不満であるようですが、キュビスム単体を究めることにそんなに意味があるとも思えないのです。いろいろな新しい思潮の影響を受けながら、自分自身の個性を確立して行ったのであれば、むしろ表現者としては好ましい変化であると言わざるを得ません。
私自身の不明を白状すれば、キュビスムというのは別にイコール抽象画ではなかったらしいということを、今日はじめて知りました。そういえばピカソがキュビスムを最初に確立したとされる「アヴィニョンの娘たち」も、抽象画か具象画かと言えば、具象画にずっと近い絵でしょう。見たままを描くことだけが具象ではなく、その絵から何か具体的な存在を見て取ることができれば、それは具象画と呼んで良いような気がします。
今回展示されていた黒田重太郎の絵など、質感の表現にキュビスム的テクニックを用いているだけで、ぱっと見た感じでは完全に具象画そのものでした。
普門暁の「鹿・青春・光・交叉」という作品は一見抽象画のようでしたが、絵の中に2頭の鹿が描かれており、なんだか隠し絵のクイズみたいでした。かと思うと岡本太郎の「まひるの顔」は、大きなひとりの顔と、小さなふたりの肢体が、見ようによって別々に見えてくるという作品で、どちらかというと錯視図形かだまし絵のようでもあります。大きい顔における眼球の部分を、小さい肢体における頭と見るわけですが、私は有名な錯視図形である「老婆と娘」(「妻と義母」とも)を連想しました。見た目は確かに抽象画っぽくはあるのですが、この絵ははたして本当に何かを「抽象」しているのでしょうか。
もちろん、抽象画について偉そうに語れるほど私には美術の素養がありませんので、馬脚を露わす前に退散したほうが良さそうですが、キュビスムであっても具象画に近いという絵が、意外にもけっこうたくさんあるということに気づいたのは今日の収穫です。
ともあれ、こんなに近いところにこれほど充実した美術館があったとは知りませんでした。今後はちょくちょく足を運んでみようと思います。
(2016.12.6.)
|