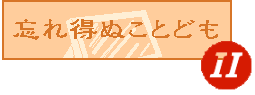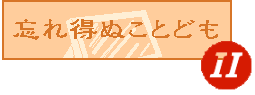|
今朝(2015年6月19日)の新聞に、文化人類学者の西江雅之先生の訃報が載っていました。
わずかな期間ながら、私は西江先生の謦咳に接したことがあります。
私の通った東京藝術大学というところは、大学とは名ばかりの専門学校であると、学生なども自虐的に言ったりしていました。
「おれたちって、実際は高卒だよなあ」
などと言い合っていたものです。附属の芸術高校(芸高)から入ってきた連中に至っては、
「おまえらはまだいい。おれたちなんか中卒だ」
とも言っていました。
要するに実技がメインで、一般教科などは教える側もおざなりだし、生徒・学生の態度もいい加減なものだったという実情を、そういう言いかたで自嘲していたわけです。
いちおう文部省(当時)管轄の大学でしたから、一般教養科目の単位の取得も義務づけられていましたが、普通の大学に較べると、一単位に対する講義時間数も少なかったし、取得要件も甘かったことは言うまでもありません。たいていの科目は出席とレポート提出だけで単位が出ましたし、試験をおこなう場合でも、ノートや参考書の持ち込みは自由であることが普通でした。
そんな状態ですが、一般教養科目を教える講師のほうは、実はかなりレベルの高い先生がたが招聘されていたのです。国立つながりということなのか、本務は東大で、週に一度だけ非常勤講師として藝大に教えに来るというパターンが多かったのではないかと思います。
まあ考えてみると、私らのレベルの学力では、難しい講義を受けても理解することは困難であるわけで、いわば市民カルチャー講座並みの、よほど易しく噛み砕いた講義をして貰わないとついてゆけません。そして、易しく噛み砕いた講義ができるためには、その学問について相当に熟達した、えらい先生でなければならないと思われます。新米の助教授(いまは准教授というのかな)くらいではなかなか務まりません。
そんなわけで、あとから考えると、本当にわれわれにはもったいないくらいのえらい先生がたが、一般教養科目の講師として招かれていたようです。
西江先生も、そういう中のおひとりでした。
死亡記事を読んでみると、西江先生は東大ではなく、外語大と早稲田の先生であったようです。
教わったときには、どれほどすごい人なのかということをまるでわかっていませんでした。略歴によると、20代で日本初のスワヒリ語辞典を編纂したというのだから、語学に関しては天才的なかただったのでしょう。そういえば私が教わっていたときも、
──だいたいどこの国へ行っても、30分も現地人に接していれば、日常会話くらいならできるようになる。
と、ご本人が言っていたのだったか、噂として聞いたのだったか、そんな話があった記憶があります。語学力が壊滅的に乏しい私には想像もできない境地です。
なおスワヒリ語というのは、中部アフリカ一帯で共通語のように使われている言語です。いわゆる通商言語というヤツで、あまり特定の部族の文化とは結びついていないらしく、そのためスワヒリ語による詩とか民謡といった古典的な言語作品というものはさほど無いそうです(近年は生まれてきているとも聞きますが)。
それでもこれを憶えておけば、中部アフリカのかなりの国で意思疎通ができるわけで、そういう言語の辞書が、半世紀前の西江青年が編纂するまで日本に無かったというのは驚くべきことです。まあ当時の日本における「国際関係」の視野には、まだアフリカのほとんどの国が入っていなかったということなのでしょう。とにかくそういう先駆的な仕事を、弱冠20代で成し遂げてしまうというのは、おそるべき早熟さと言えるでしょう。
昭和59年に「アジア・アフリカ賞」を受賞していますが、まさに私が西江先生の講義を聴いていたその年でした。
文化人類学と言っても、それまでなんの素養も無く、どんなことを扱う学問なのかすらたいして理解しておらず、学年はじめに配られるシラバスを読んでなんとなく面白そうだと思ったから受講することにしたばかりでした。
最初の講義で「エスノセントリズム(自民族中心主義)」という言葉を教わりました。世界中どこの民族も、自分たちの文化を基準にして他を見てしまうものだというわけですが、先生の口ぶりでは、それが別に「悪いこと」であるようには感じられなかったのが意外でした。自分(たち)中心に物事を見るというのは、どことなく「感心できないこと」であるという意識が当時の私にはありました。同じように思っている人はいまでも多いのではないでしょうか。なんでもやたらと「グローバル化」が善しとされる風潮はその顕れと言えましょう。
しかし、グローバルがなんでも善いというわけでもなさそうです。日本人には日本人としての視座があって悪いことはありません。それが万国共通の見かたであるという錯覚さえ起こさなければ問題はないのです。
先生の講義では繰り返し、他の文化から見たときに日本の習俗が奇異に見えるという例証を挙げられていました。
教室の女子学生たちを見まわして、
「イスラムの国に行くでしょう。そうするとこの教室に居るあなたがたは全員、ハダカなんですよ」
女子学生たちが
「え〜〜」
と騒ぐと、
「あなたがたは『服を着ているのに』と思ってるでしょう。でもあちらの文化から見ると、腕を出している、顔を出している、脚を出している。それでハダカということになってしまうんです。向こうの人が日本に来れば、女性がみんなハダカで歩いていると思うでしょうね」
誰もが自分の文化を通して物事を見ているのだという説明として、衝撃的かつとてもわかりやすいお話でした。
「逆に、服を着るというのも文化ですから、北極圏の寒いところで上半身に何も着ないで平気でいる人々だって居るわけです」
「風邪をひいちゃうんじゃないですか?」
学生が訊ねると、
「いや、文化ですから。私たちも、寒い日でも顔は出していることが多いでしょう。同じように、肩や背中をはだけていても、そういう人たちはなんともないんです」
エスキモーの完全防備っぽい防寒服を思い浮かべると、本当かなあと首を傾げたのですが、北欧あたりでは気温が5度くらいでも……というか5度くらいまで上がると、みんな平気で半袖で歩いています。われわれにはとても寒くて真似はできません。それどころか、スウェーデンだったか、乳母車に乗せた赤ちゃんを何時間も屋外に放置するという習慣さえあるそうです。日本の赤ちゃんだったらたちまち凍えて熱を出してしまうでしょうが、こういう話を聞くと、なるほど「体質」すら「文化」なのだなと納得せざるを得ません。
他にも、ゴキブリを食物の範囲に含めている民族の話とか、ともかく意外性のあるトピックを次々に講義していただきました。それらがすべて、書物からの知識ではなく、先生ご自身のフィールドワークにより得られた知見であるというところが素晴らしかったと思います。
わずかな期間でしたが、とても面白い講義で、毎週の文化人類学の時間が待ち遠しく感じられたものでした。大学で学んだ一般教養科目の中でも、いちばん印象に残っており、しかもその後の自分のものの見かたに大きな影響を及ぼしているようです。
講義期間が終わってからは西江先生にお会いすることもありませんでしたし、著書を拝読したこともありません。新潮文庫かどこかでエッセイのような本が出ているのを見つけたときに、
──おお、これは……
と注目したものの、そのとき所持金が少なかったのだったかどうだったか、結局買わずに書店を離れてしまいました。
そんな程度で、縁はいかにも薄かったと言わざるを得ませんが、訃報に接してみるとあれこれ思い出され、もう少し講義後などにお話しを伺っていれば良かったと、詮無いことながら30年前を後悔したりしました。あらためて著書を探して読んでみようかとも思います。
ご冥福をお祈りいたします。
(2015.6.19.) |