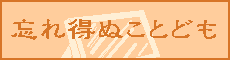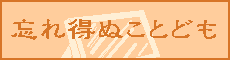|
私の出入りしているふたつほどの音楽サイト(りっちゃんの「クラシック音楽の部屋」と岡村英之さんの「20世紀の音楽(エンジョイ派)」)に、音楽に関する質問コーナーのようなものがあって、訪問者の質問に対し、それに答えられる別の訪問者が回答するという形になっています。ネットならではの方法で、なかなかよいと思います。
行きがかり上、私はそこで回答をすることが多いのですが、これが結構手間取る作業です。
自分の知っていることを書くだけなのだから楽なようですが、そうは行きません。いい加減なことを書いてはいけないと思いますので、事典などで調べ直したりすることもしょっちゅうです。そうすると、自分ではわかっていたつもりのことが、案外あやふやだったりして、勉強し直しのおもむきを呈してきます。
それに、質問者は多くの場合、あまりよく知らない相手ですから、その知識レベルもわかりません。回答したところで、回答に使われている概念や術語自体が理解できない、ということも起こり得ます。そうすると、それらの基礎的なところから、かみ砕いて説明する必要が生じます。そうなると、それらの概念を理解しているだけではなく、自分の言葉で表現できるところまで身についていなくてはならないということに気がつきます。
漠然とわかったつもりになっていたことが、
――あっ、そういうことだったのか。
と、回答を書きながらはじめて実感されるということも、珍しくはありません。
質問に回答を書くことは、自分のための勉強にもなるようです。というより、そうした作業こそ、自分にとっての最高の勉強方法なのではないかと、最近つくづく思うようになりました。
ことは知識だけの問題ではありません。
幼い頃からピアノを習っていましたが、先生に言われてきたことが、本当に実感として理解できたのは、実は自分が生徒にピアノを教えるようになってからのことでした。歌を歌うコツがわかってきたのは、合唱指導をはじめて発声練習などを見るようになってからのことでした。
人に教えることこそ勉強のもっとも効果的な方法であり、むしろ教えないことには勉強が本当には身につかないのではないか、とすら思えます。
幕末には江戸や大阪、京都などに多くの塾がありました。有名なところでは緒方洪庵(おがたこうあん)の「適塾」などがあり、ここは大村益次郎、福沢諭吉、大鳥圭介などそうそうたる卒業生を輩出しています。今の学校と違い、みな、洪庵先生の学問や考え方、人柄などに惹かれて入塾しているわけです。
ところが、洪庵先生自身が講義を行うのは、せいぜい月に数回くらいなものだったそうです。あとはどうしていたかというと、代講の先生もいないことはなかったでしょうが、もっぱら、先輩の塾生が指導に当たったというのです。
先生が非常に多忙だったことは確かですが、現代の感覚からすると、塾を構えながら月に数回しか講義をしないのでは、怠慢と言われても仕方がないでしょう。
しかし考えてみると、先輩の塾生たちは、後輩を指導することによって、より自分の学問を深められたというものではないでしょうか。
――自分の勉強に忙しくて、他人を教えている暇などない。
というような連中は、結局大成しなかったように思われます。
教えるということは、知識や技術をすっかり自分のものにした上で、それを自分なりにかみ砕いて表現できなければなりません。この最後の部分をおろそかにしては、勉強は身につくものではないのです。
もちろん、教えさえすればそれでよいかというとそんなことはなく、何も考えずに教えるのはただの知識の伝達に過ぎません。教える側に、これは自分自身の勉強なのだという意識が常にあってこそ、自分にも相手にもよく理解させられるというものです。
――先生と呼ばるるほどの馬鹿は無し
と、昔から川柳にも謳われていますが、学生アルバイトの家庭教師から大学教授に到るまで、人から先生と呼ばれるほどの人は、ついつい慢心しがちです。私も方々で先生と呼ばれる立場にありますが、教えることと勉強することは一体なのだということを常に肝に銘じておかなくてはならないと思います。
(1998.5.17.)
|